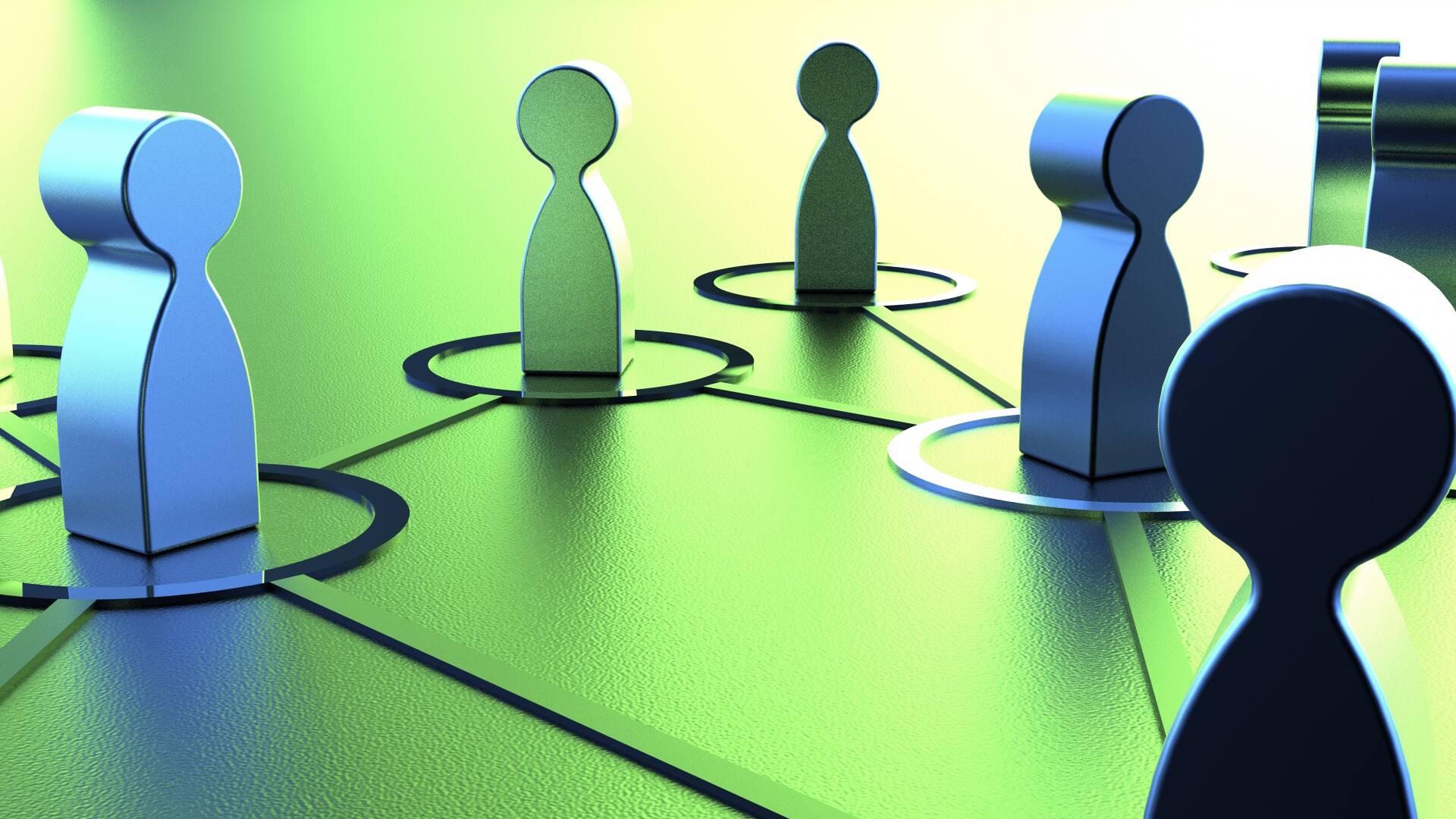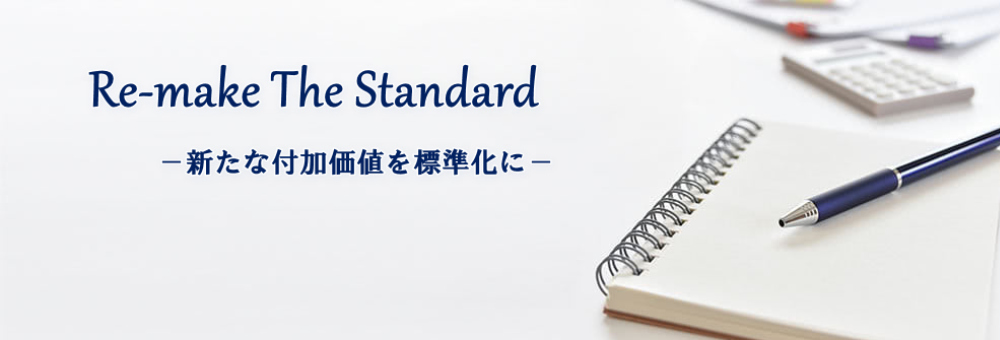
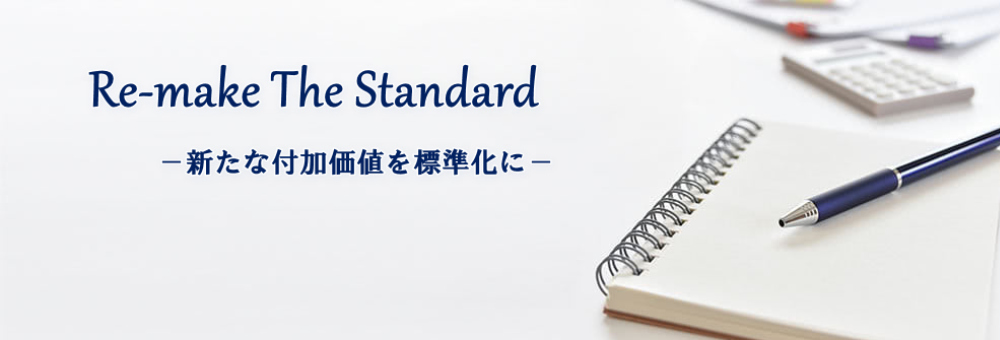
�|�e���V�����̗p�Œ蒅������3�̎d�g���o���̈琬��1�N�ȓ��̗��E��h�����@
**�o���̃|�e���V�����̗p�����s���錴���́A���Ќ�́u����M���b�v�v�ɂ���܂��BOJT�Ƃ������̕��u����߁A�@�̌n�I�Ȓm�����C�A�A�i�K�I�Ȏ����P���A�B����I�ȃp�t�H�[�}���X���r���[�Ƃ����琬�̎d�g�݂��\�z���邱�ƂŁA���͊m���ɐ������A�蒅���܂��B
�u�f���Ő^�ʖڂ����A�����w�K�ӗ~�������B�f���炵���|�e���V�������߂���ނ��v
�������̗p�s��̒��A�悤�₭�����o�����_�C���̌��B�傫�Ȋ��҂����߂č̗p�����A���̎��o���S���҂̖������A���Ȃ��͐S����M���Ă����͂��ł��B
�������A���Ђ��甼�N���߂���������A����̉_�s�����������Ȃ�n�߂܂��B�o���}�l�[�W���[����́A�u���܂Ōo���Ă������悤�ȃ~�X���J��Ԃ��Ă���v�u�w���������Ƃ�����炸�A�����ōl���ē������Ƃ��Ȃ��v�Ƃ������A����������̕������Ă��܂��B
�����āA���Ђ��炿�傤��1�N���o���B���̎��́A�u��g��̓s���ɂ��v�Ƃ�����^�����i�ɍ����A�Â��ɉ�Ђ������Ă����̂ł��B
����ɂ́A�琬�ɂ��������ԂƘJ�͂����ʂɂȂ����Ƃ����k�J���ƁA�u��͂�A�����Ă�����͂��̗p����ׂ��������v�Ƃ����A�d�ꂵ�����߂̋�C���Y�������B
�����A���̂��܂�ɂ��߂����V�i���I�ɁA�����ł��S�����肪����̂Ȃ�A��x���������~�܂��āA���₵�Ă������������̂ł��B
���̔ߌ��́A�{���ɍ̗p�������́g�|�e���V�����s���h�������������̂ł��傤���H
����Ƃ��A�_�C���̌��J�ɖ����グ�邽�߂�**�g�d�g�݁h�Ɓg���h**���A���̉�Ђɂ͍��{�I�Ɍ����Ă��������ł͂Ȃ��̂ł��傤���H
�Ȃ����o����1�N�Ŏ��߂�̂��H�����敾������uOJT�̎O�d��v
**�|�e���V�����l�ނ��炽�����߂Ă��܂��̂́A�u�����鑤�E���e�E����鑤�v�̎O�҂����E���}����u����M���b�v�v�������ł��B����C����OJT�ł͂��̍\�����͉����ł��܂���B
�����̌o�c�҂�l���S���҂́A�u���̈琬�͌����OJT�iOn-the-Job Training�j�ʼn��Ƃ��Ȃ�v�ƐM���Ă��܂��B�������A���́g�P�Ӂh�Ɓg����C���h�������A�|�e���V�����l�ނ̉��E�݁A�������E�������ő�̌����ƂȂ��Ă��邱�ƂɁA�������͋C�Â��Ȃ���Ȃ�܂���B
����̊�Ƃ��ׂ��Ă���̂́A�l�̓w�͕s���Ȃǂł͂Ȃ��A**�u�̗p��̋���M���b�v�v**�Ƃł������ׂ��A���[���\�����Ȃ̂ł��B���̖��́A�O�̐[���Ȍ��E���琬�藧���Ă��܂��B
���E�@�F�����鑤�i����}�l�[�W���[�j�̌��E
�܂��A�����闧��ɂ��錻��̃}�l�[�W���[���y�Ј����g���A���͂���E���}���Ă��܂��B�ނ�̑����́A���g�̖ڕW�B���ƕ����̃}�l�W�����g�𗼗�������v���C���O�}�l�[�W���[�ł��B���X�̐����������A�������Z�̒��ߍ�ƂƂ����������ɒǂ��A�V�l�̈琬�ɑ̌n�I�Ɏ��Ԃ��������ƂȂǁA�����I�ɕs�\�Ȃ̂ł��B
�ނ炪�ł���̂́A�ꓖ����I�Ȏw���ƁA�ڂ̑O�ŋN�����~�X�ւ̑ΏǗÖ@�I�ȃt�B�[�h�o�b�N�����B�u�w�������Ċw�ׁv�Ƃ����̂́A�琬�Ɏ��Ԃ�������]�T���Ȃ����Ƃ̗��Ԃ��ɑ��Ȃ�܂���B
���E�A�F��������e�i�Ɩ��j�̌��E
���ɁA������ׂ��Ɩ����e���̂��̂ɂ����E������܂��B�o���̎����́A��L����Ŋw�Ԃ悤�ȕ��ՓI�Ȓm�������ł́A���ꑾ���ł��ł��܂���B�����ɂ́A���N�̊Ԃɒ~�ς��ꂽ�u���ГƎ��̉�v�������[���v��u���̎������L�̐����t���[�v�Ƃ������A������**�g�Öْm�h**�����݂��܂��B
�������A�����̈Öْm�́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A���͉����ꂽ�}�j���A���Ƃ��Ă͑��݂��܂���B���ׂẮA�S���҂̓��̒��ɂ����Ȃ��A�Ɩ��͋ɓx�ɑ��l�����Ă��܂��B����ȏŁA�V�l�͂ǂ�����ċƖ��̑S�̑���͂߂悢�̂ł��傤���B
���E�B�F����鑤�i�V�l�j�̌��E
�����čŌ�ɁA����鑤�̐V�l���܂��A�[���Ȍ��E�ɒ��ʂ��܂��B���Ђ�������̐V�l�ɂƂ��āA**�u����������Ȃ��̂�����A������Ȃ��v**�Ƃ����̂��{���ł��B
�f�ГI�Ȏw���̈Ӗ��������ł����A���₵�悤�ɂ��A�����ǂ����������̂�������Ȃ��B���̔����ǂ���̏́A�V�l�̎��M�Ɗw�K�ӗ~��e�͂Ȃ��킬���Ƃ��Ă����܂��B�̌n�I�Ȓm���Ƃ����y�䂪�Ȃ��܂܁A�����ڂ̑O�̍�Ƃ����Ȃ����X�B�������Ă������������ꂸ�A��Ђւ̍v���������ĂȂ��܂܁A�ނ�̐S�͐Â��ɐ܂�Ă��܂��̂ł��B
����**�u�O�d��v**�������A�u�̗p��̋���M���b�v�v�̎��Ԃł��B����́A�l�̎����̖��ł͂Ȃ��A�琬���l�̑P�ӂ⌻��̓w�͂Ɋۓ������Ă����A�g�D�̎d�g�݂��̂��̖̂��Ȃ̂ł��B
������F�uOJT�v����u�̌n�I�琬�v���O�����v��3�v�f�ւ̓]��
������́A�琬���u�d�g�݉��v���邱�Ƃł��B��̓I�ɂ͇@�̌n�I�Ȓm�����C�A�A�i�K�I�Ȏ����P���A�B����I�ȃp�t�H�[�}���X���r���[��3�̗v�f��g�ݍ��킹���v���O������v�E���s���܂��B
�ł́A�ǂ�������̕��̘A����f����A�|�e���V�����̗p�𐬌��ւƓ������Ƃ��ł���̂ł��傤���B
�����́AOJT�Ƃ������́u���u�v��u�ۓ����v����������߁A**���m�ȈӐ}�Ɛv�v�z���������u�I���{�[�f�B���O�E�v���O�����v**�ւƁA�琬�̂���������{����]�����邱�Ƃł��B
��������琬�v���O�����ɂ́A���ʂ���O�̏d�v�ȗv�f������܂��B
�v�f�@�F�̌n�I�Ȓm���C���v�b�g�iOff-JT�j
**�o���̖��̍����́A�m���s���ł��B**�܂��́A�����̑O�ɁA�S�Ă̓y��ƂȂ�OS�i�I�y���[�e�B���O�V�X�e���j���C���X�g�[�����鎞�Ԃ��K�v�ł��B
- �o���̌��������F ��L2�����x���̒m�������Ŗ@�̊�{�ȂǁA�S�Ă̔��f�̋��菊�ƂȂ镁�ՓI�ȃ��[�����w�ђ����܂��B
- ��Ђ̌��@�i�o���K���j�F ���ГƎ��̊���Ȗڃ��[���A�o��Z�̋K���A�g�c�̃t���[�ȂǁA�Г��̌������[�����C���v�b�g���܂��B
- �c�[���̑�����@�F ��v�V�X�e����֘A�c�[���̊�{�I�ȑ�����@���K�����܂��B
���̓y�䂪�����ď��߂āA�V�l�͎���l���A���p����͂�g�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�v�f�A�F�i�K�I�ɐv���ꂽ�����P���iOJT�j
�m�����C���v�b�g������A���͎��H�ł��B�������A��݂����ɋƖ���U��̂ł͂���܂���B�V�l�̐����X�e�b�v�ɍ��킹�āA���m�ȃ��[�h�}�b�v��v���܂��B
- Step 1�i1�����ځj�F �܂��͌����o�[��o��Z�Ƃ������A��^�I�ʼne���͈͂̏��Ȃ��Ɩ�����S�����܂��B�S�[���F��l�Ń~�X�Ȃ������ł���B
- Step 2�i3�����ځj�F ���|���┃�|���̊Ǘ��ȂǁA�������Ƃ̘A�g���K�v�ȋƖ����w�т܂��B�S�[���F�S���҂Ɖ~���ɃR�~���j�P�[�V����������B
- Step 3�i6�����ځj�F �������Z�̕⏕�Ɩ��ɒ��킵�܂��B�S�[���F���Z�X�P�W���[���𗝉����A�S���ӏ��̐��l���m��ł���B
���̂悤�ɁA�X���[���X�e�b�v�Ő����̌���ς܂��邱�Ƃ��A�m�����X�L���ւƏ������A�V�l�̎��M�Ǝ�̐�����݂܂��B
�v�f�B�F�p�t�H�[�}���X���r���[�ƋO���C��
�ł��d�v�Ȃ̂��A�C���v�b�g�����m�����A�����Ő������g���Ă��邩���m�F���A�O���C�������v���Z�X�ł��B����́A�s����Y�݂���ł͂Ȃ��A�v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ă̐����𑣂����߂́u�R�[�`���O�v�̎����ł��B
- ����I�i�T���E�����j�ȃ��r���[�F �}�l�[�W���[�����Ԃ��m�ۂ��A�u�Ȃ��A���̎d��͂��̊���Ȗڂŏ��������̂��H�v�Ƃ�����**�uWhy�v**��₤���ƂŁA����̗��ɂ��錴�������̗���x���m�F���܂��B
- ��̓I�ȃt�B�[�h�o�b�N�F �ǂ������_�Ɖ��P�_����̓I�ɓ`���A���̃��x���ɓ��B���邽�߂̖��m�ȉۑ��ݒ肵�܂��B
- ���̖ڕW�ݒ�F ���̃��r���[�܂ł̋�̓I�ȖڕW�����L���A�����ւ̃}�C���X�g�[���m�ɂ��܂��B
���̂悤��**�u�d�g�݁v**���\�z���邱�ƁB���ꂱ�����A���ʓI�Ɍ���}�l�[�W���[�̕��S�����I�Ɍ��炵�A�V�l�̑�����͉��ƒ蒅����������A�B��ɂ��čŒZ�̃��[�g�Ȃ̂ł��B
RSTANDARD�̒��l�F���́u�琬�̎d�g�݁v�A�ۂ��Ƃ����܂�
�u�琬�̎d�g�݁v�����Ђō\�z���郊�\�[�X���Ȃ���Ɨl�̂��߁ARSTANDARD���O���̐��琬����Ƃ��ċ@�\���A�̗p��̊m���Ȑ����ƒ蒅���T�|�[�g���܂��B
�u���z�͂悭���������B�������A���Ђɂ���Ȏ�����琬�v���O�������[������\�z���郊�\�[�X���m�E�n�E���Ȃ��v
�����܂œǂ�ł������������̒��ɂ́A���������Ă�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂��C�����́A�ɂ��قǂ悭������܂��B
�����炱���A������RSTANDARD�́A�̗p�̃v���t�F�b�V���i���ł���Ɠ����ɁA�o���l�ވ琬�̃v���t�F�b�V���i���Ƃ��āA�M�Ђ̉ۑ�����̃p�[�g�i�[�ł��肽���ƍl���Ă��܂��B
R�̌o���l�ޏЉ��ł��Љ�Ă���**�w�y���� 4�z ���Ќ�̑���͉��ƒ蒅�����w�琬�x���v���O�����x�x**�́A�P�Ȃ�̗p�̕t���T�[�r�X�ł͂���܂���B
����́A�M�Ђ�������琬�Ɋւ��邠����ۑ�??���\�[�X�s���A�m�E�n�E�s���A���ԕs��??���������邽�߂ɐv���ꂽ�A**����M�Аꑮ�́u�O���̐��I�Ȉ琬����v**�Ƃ��Ă����p����������T�[�r�X�ł��B
������������̂́A�̗p�����l�ނɁA���В��ォ��v���t�F�b�V���i���ɂ��̌n�I�Ȍo�����C���Ă��炤�d�g���ł��B
����ɂ��A�M�Ђ́A
- �Г��̃��\�[�X���������ƂȂ��A����̕��S�𑝂₳���ɁA
- �̗p�����l�ނ́A�m���Ȑ����Ƒ�����͉��A�����Ē蒅�Ƃ�������
��`�����Ƃ��ł��܂��B����́A�琬����������悤�Ƃ��Ď��s���A�̗p�R�X�g�ƌ���̔敾�Ƃ�����d�̑������郊�X�N��������邽�߂́A�m���Ȗ����ւ̓����ł��B
�A�N�V�����F�܂��́u�b���Ă݂�v���Ƃ���n�߂܂��H
**�|�e���V�����̗p�̐��ۂ͓��Ќ��3�����Ō��܂�܂��B�܂��͂��C�y�ɂ����k���������B�M�Ђ̏����A���̈����ꏏ�ɍl���܂��B
�|�e���V�����̗p�̐��ۂ́A����ʒm���ɃT�C������������u�Ԃł͂Ȃ��A���Ќ�̍ŏ���3�����ŁA����9�������܂�܂��B
�̗p���u�S�[���v�Ƒ�����̂��A����Ƃ������̃R�A�l�ނ���Ă�u�X�^�[�g�v�Ƒ�����̂��B���̈ӎ��̈Ⴂ���A1�N��̖�����傫�����E���܂��B
�����A�M�Ђ��{�C�Ŏ��̈琬�ƌ��������A�o������̖�����z���Ă��������Ƃ��l���Ȃ�A���Ј�x�A�������ɋM�Ђ̏������������������B
�u�����������������������Ȃ��v�u�܂��͏����W�����������v??**���̂悤�ȁA���R�Ƃ����i�K�ł̂����k���قƂ�ǂł��B**�����ȉc�Ƃ͈�������܂���̂ŁA�����S���������B
�M�Ђ̉ۑ�����A���̈����ꏏ�ɍl����p�[�g�i�[�Ƃ��āA�������������ɗ��Ă邱�Ƃ����邩������܂���B
�����C�y�ɂ����k����������
�܂Ƃ�
�|�e���V�����̗p�́A�����āu�q���v�ł͂���܂���B
����́A�������琬��**�u�d�g�݁v**��������A��Ƃ̖�����S���l�ނƂ����A�����ɂ��ウ���������Y�ݏo���A**�ł��m���Ń��^�[���̑傫���u�����ւ̓����v**�Ȃ̂ł��B
RSTANDARD���A�̗p�Ƃ����u�����v����A���̐�̈琬�E�蒅�Ƃ����u���Ќ�v�܂ł��A�ӔC�������Ĉ�C�ʊтł��x�����܂��B�M�Ђ̌o������̋P�������������A�������Ƌ��ɑn��グ�Ă����܂��傤�B
����ɏڂ����m�肽�����ցF�悭���邲����iFAQ�j
�o���̎�肪���߂Ă��܂��A�{���̌����͉��ł����H
�|�e���V�������u�{���̎����X�L���v�ւƓ]��������琬�̎d�g�݂��Ȃ����Ƃ����{�����ł��B�{�l�̈ӗ~�s���ł͂Ȃ��A�m�����X�L���ւƑ̌n�I�Ɉ�Ă���������Ă��邽�߁A�����������ł����ɗ��E�Ɏ���܂��B
OJT�����ł́A�Ȃ��_���Ȃ̂ł��傤���H
�̌n�I�Ȓm���Ƃ����y�䂪�Ȃ��܂܂�OJT�́A�P�Ȃ�u�ꓖ����I�ȍ�Ǝw���v�ɂȂ肪��������ł��B���������𗝉����Ă��Ȃ����߉��p���������A�����鑤�E����鑤�o���̕��S�𑝂₷�����̌��ʂɏI����Ă��܂��܂��B
�琬���n�߂�ɂ�����A�����ł��d�v�ł����H
**�����ɓ���O�́A�̌n�I�Ȓm���C���v�b�g�i���w�j**�ł��B��L��Ŗ@�Ƃ��������ՓI�ȃ��[���ƁA�o���K���Ƃ����Г����[�����ŏ��ɃC���X�g�[�����邱�ƂŁA���̌�̎����P���iOJT�j�̌��ʂ�����I�ɍ��܂�܂��B
�p�t�H�[�}���X���r���[�ł́A����b���ׂ��ł����H
�s����Y�݂����Ƃł͂Ȃ��A�u�Ȃ��A���̂悤�ɏ��������̂��H�v�Ƃ����₢��ʂ��āA�{�l�̒m���̗���x�Ǝ��H�x���m�F���邱�Ƃ��ړI�ł��B�v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ă̐����𑣂����߂́A��̓I�ȃt�B�[�h�o�b�N�Ǝ��̖ڕW�ݒ���s���܂��B
���ǁA�琬�ɂ͌���}�l�[�W���[�̎��Ԃ������̂ł͂���܂��H
�u�d�g�݉��v����Ă��Ȃ��琬�������A�}�l�[�W���[�̎��Ԃ�D���܂��B�����ɑ̌n�I�Ȍ��C���s���A�琬�v���O������v���邱�ƂŁA�ꓖ����I�Ȏ���Ή���~�X�̎蒼���Ƃ�����**�u������������͂����������ʂȎ��ԁv**��啝�ɍ팸�ł��܂��B
���ЂɈ琬�̃m�E�n�E������܂���B�ǂ�����Ηǂ��ł����H
�O���̐��@�ւ����p���邱�Ƃ��ł������I�ł��BRSTANDARD�̂悤�Ȑ��@�ւ́A�����̊�Ƃ��x���������тɊ�Â��A���ʂ������ꂽ�琬�v���O������ۗL���Ă��܂��B�琬���A�E�g�\�[�X���邱�ƂŁA��Ƃ͖{���̎��ƂɏW���ł��܂��B
���̃��`�x�[�V�������ێ�����R�c�͂���܂����H
���m�Ȑ������[�h�}�b�v�ƁA�i�K�I�Ȑ����̌��ł��B�v���ꂽ�����P����ʂ��āu�ł��Ȃ��������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�v�Ƃ����������������A���r���[�̏�ł��̐�������̓I�ɏ��F���邱�Ƃ��A�v���Ƃ��Ă̍v���ӗ~�����߂܂��B
�琬�ɂ�����R�X�g�ƃ��^�[���̍l�����������Ă��������B
�琬�R�X�g�́A�����ւ̓����ł��B�������E�ɂ��č̗p�R�X�g��A����̐��Y���ቺ�Ƃ�����������h�����ƂŁA�����z�����郊�^�[���i�l�ނ̒蒅�E��͉��j�����҂ł��܂��B
RSTANDARD�̈琬�x���́A���ЂƉ����Ⴄ�̂ł����H
�l�ނ́u�̗p�v����u�琬�E�蒅�v�܂ł���C�ʊтŐv���A��������_�ł��B�M�Ђ̉ۑ�ɍ��킹���œK�ȍ̗p�ƁA���̌�̐������Z�b�g�ł��x�����܂��B
�琬�v���O���������鎞�Ԃ�����܂���B�ǂ�����Ηǂ��ł����H
�܂��͊O���̐��Ƃɂ����k���������BRSTANDARD�ł́A�M�Ђ̌���ɍ��킹�āA�����ɓ����ł���琬�v���O����������ĉ\�ł��B�̗p�ƈ琬�̉ۑ���ɉ������܂��B