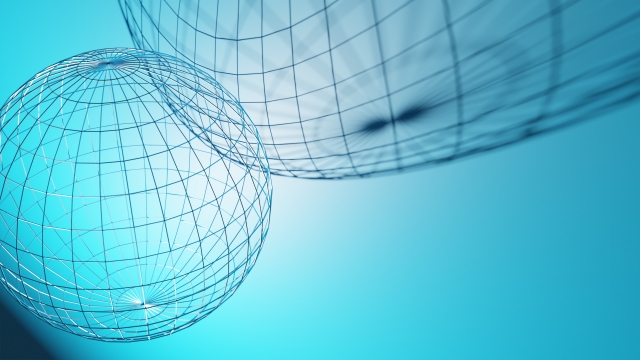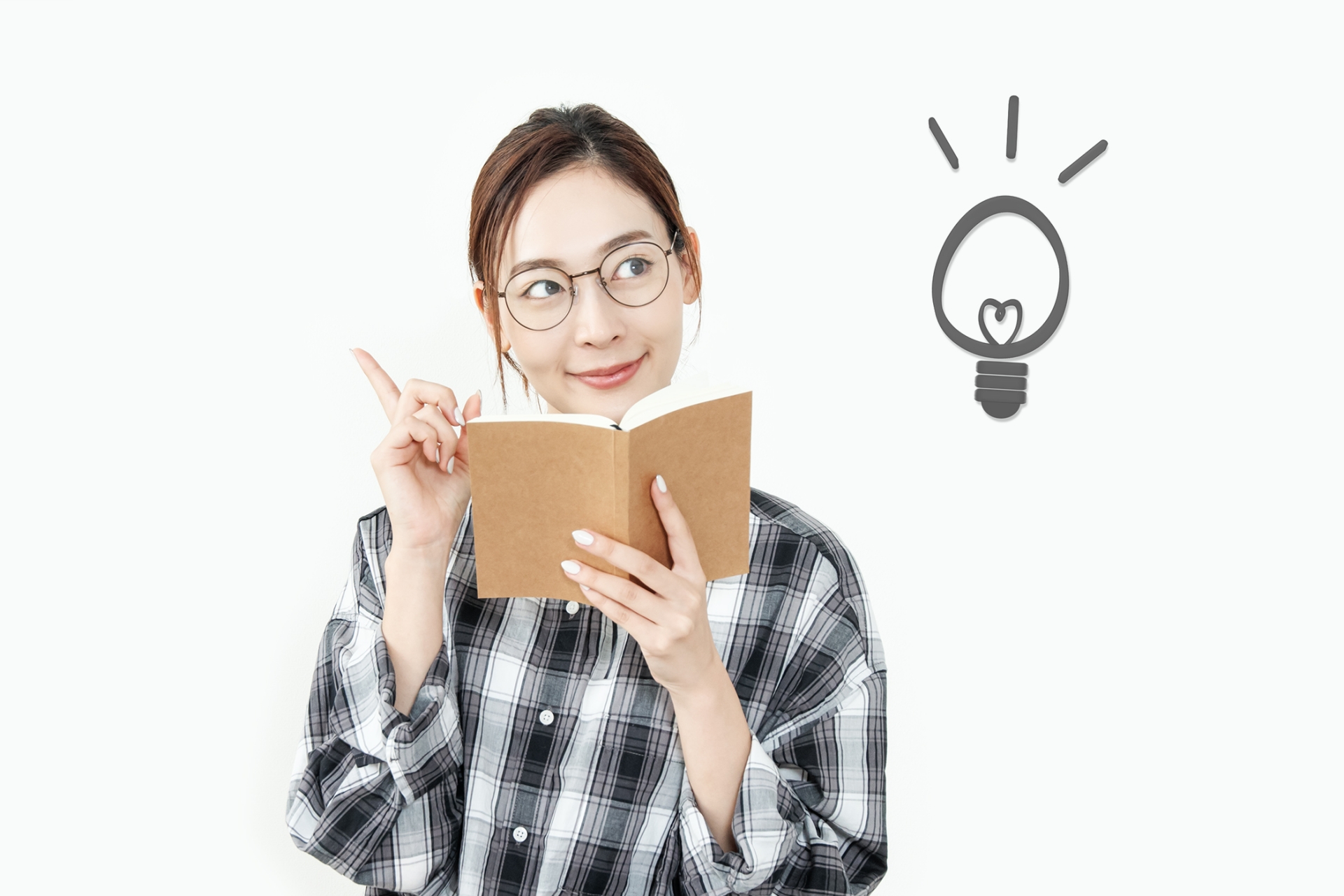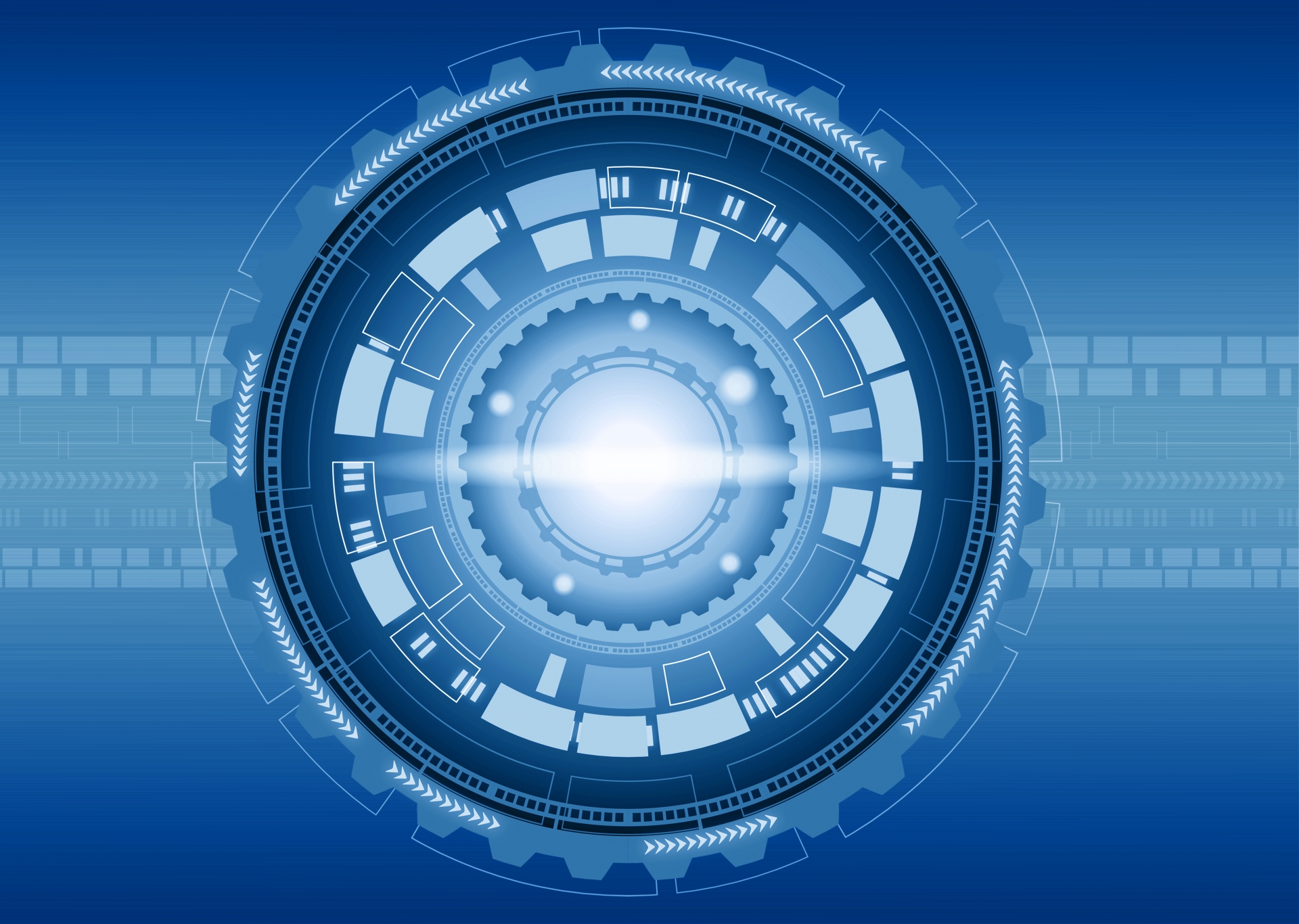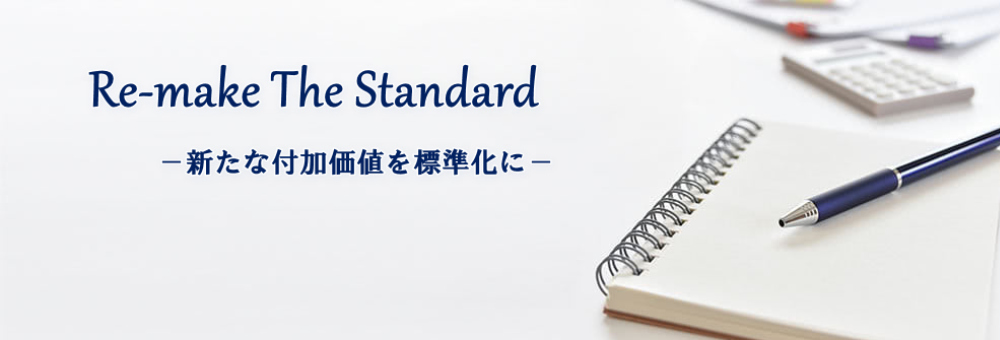
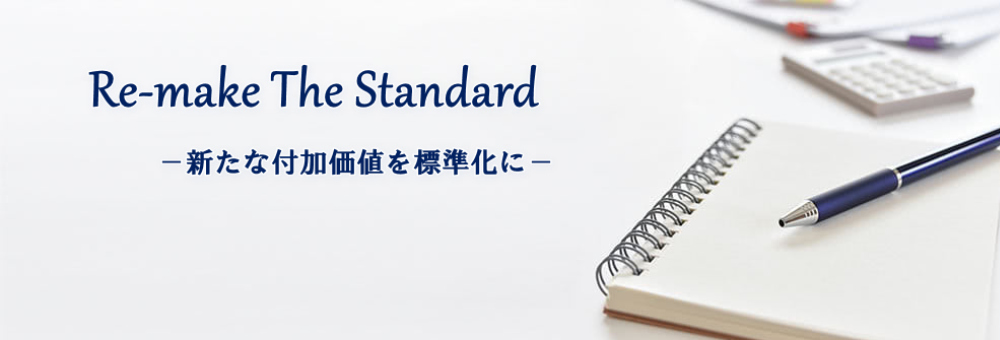
���Z���Ƃ́H�������〈��


�������RSTANDARD
�o����l�ވ琬�Ȃǂɂ����邨�𗧂����M���B �������Ă���������{�m������𗧂m�E�n�E�Ȃ�RSTANDARD�Ȃ�ł͂̎��_�Ə��ʂł��͂����܂��B
��Ƃ̍������m�F���邽�߂ɂ́A�������\��ǂޕK�v������܂��B�Ƃ͂����A���߂č������\��ڂɂ���ꍇ�́A�ǂݕ���������Ȃ��č��邱�Ƃ�����ł��傤�B�����ŁA���̋L���ł͌��Z���̌����⏑�����ɂ��ĉ�����Ă����܂��B���Z���̌������K������A��Ђ̌o�c��������܂��B���ЎQ�l�ɂ��Ă��������B
�o���A�E�g�\�[�V���O�ŋƖ��������E�R�X�g�팸
�o���A�E�g�\�[�V���O�Ȃ�RSTANDARD
���Z���Ƃ�
���Z���Ƃ͍������\�̈�ʓI�ȌĂѕ��ŁA��Ƃ̍�����o�Ϗ�Ԃ��������ނ̂��Ƃł��B�Ђƌ��Ɍ��Z���ƌ����Ă��A���ۂɂ͂�������ނ�����܂��B
| ���Z���̎�� | �T�v |
| �ݎؑΏƕ\ | ��Ƃ̎������B�E�����^�p�̏������� |
| ���v�v�Z�� | ��Ƃ̉c�Ɗ����̗��v���p�������� |
| �L���b�V���t���[�v�Z�� | �����̗��ꂪ�킩�� |
�����3�̏��ނ͍������\�̒��ł���ʓI�Ȃ��̂ō��킹�āu�����O�\�v�ƌĂ�Ă��܂��B���̂����ǂꂩ1�ł�������Ə�s������̂ŁA3�Z�b�g�Ō��邱�Ƃ���ł��B
�ł́A�Ȃ����Z�����쐬����K�v������̂ł��傤���B���Z�����K�v�ȏ�ʂ́A�ȉ��̒ʂ�ł��B
- ���Z�@�ւɗZ����\�����ނƂ�
- ���Ђ̌o�c���m�F�������Ƃ�
- �����ƂɌo�c�����Ƃ�
- �m��\�����s���Ƃ�
���Z�����K�v�ȗ��R�͈ꌾ�Ō����ƁA��Ƃ����Z�@�ւ�����A����ɑ��č�����o�c����邽�߂ł��B��L�̂悤�ȏ�ʂŌ��Z��������A���̊�Ƃ�1�N�Ԃ��̂悤�ɉc�Ɗ����E�������B�E�������s��������������܂��B�܂��A�m��\���̍ۂɒ�o������A���Ђ�1�N�Ԃ̌o�c��U��Ԃ����肷��ۂɂ��𗧂��܂��B
�֘A�L���F���Z�Ɩ����s�����R�E�����́H��̓I�Ȏ菇��K�v���ށE�������̕��@
���Z���̌���
�ł́A���Z���͂ǂ̂悤�Ɍ�����̂Ȃ̂ł��傤���B��������́A�ݎؑΏƕ\�A���v�v�Z���A�L���b�V���t���[�v�Z���̂��ꂼ��̌����ɂ��ĉ�����Ă����܂��B
�ݎؑΏƕ\�̌���
�ݎؑΏƕ\�͊�Ƃ̎������B�E�����^�p�̏������鏑�ނŁA�ݎؑΏƕ\��ǂݎ�邱�ƂŁA���̊�Ƃ̍����𗝉��ł��܂��B
�܂��A�ݎؑΏƕ\�ɂ�1���[��������܂��B����́A�����̍��v�z�ƉE���̍��v�z��K����v�����邱�Ƃł��B����������������A�ݎؑΏƕ\�́u�o�����X�V�[�g�v�������́uB-S�v�iBalance Sheet�j�Ƃ��Ă�܂��B
�ݎؑΏƕ\�͊�{�I�Ɂu���Y�v�u���v�u�����Y�v��3�̗v�f�ō\������Ă��܂��B���ꂼ��̗v�f�͈ȉ��̂悤�ȈӖ�������܂��B
| ���Y | �����������͔�������ɂȂ���́A�u�����I�ɓ����Ă������ |
| ���� | ��Ђ������Ă���؋� |
| �����Y | ��Ў��̂������Ă��邨�� |
����3�̗v�f�́A�����5�̃u���b�N�ɕ�����A�ȉ��̂悤�ɋL�ڂ���܂��B
| ���Y �@?�������Y ������ ���a�� ������` �����|�� ���L���،� ���I�����Y �A�Œ莑�Y ���y�n ������ ���@�B | ���� �B�������� ���x����` �����|�� �������� ���Z���ؓ��� �C�Œ蕉�� �������ؓ��� ���Ѝ� |
| �����Y �D�����Y �����{�� �����{��]�� |
5�̗v�f�͂��ꂼ��ȉ��̂悤�ȈӖ��������Ă��܂��B
| �������Y | 1�N�ȓ��Ɍ����ɂł��鎑�Y |
| �Œ莑�Y | 1�N�ȓ��Ɍ������ł��Ȃ����Y��A�x�����K�v���Ȃ����Y |
| �������� | ��Ƃ�1�N�ȓ��Ɏx�������A�܂���1�N�ȓ��Ɏ��v�ɐU��ւ��镉�� |
| �Œ蕉�� | ���Z����1�N�ȏォ���Ďx�������� |
| �����Y | �ԍς̋`���̂Ȃ����Y |
���̂悤�ɁA�ݎؑΏƕ\��5�̃u���b�N�ɕ�����Ă���̂ł����A�ǂ̂悤�ɓǂݎ������̂ł��傤���B��Ƃ��쐬�����ݎؑΏƕ\�́A�ȉ��̂悤�ɓǂݎ��܂��B
| ���Y ���ǂ̂悤�Ȏ��Y��ێ����Ă��邩 ���������ł�����̂��A�����łȂ��� | ���� �����̂悤�ȕ�������Ă��邩 �������ɕԍςł�����̂��A�����łȂ��� |
| �����Y �����{���͂ǂꂭ�炢����̂� |
�����́u���Y�v����́u�����̎g�����v��������A�E���́u���v�u�����Y�v����́u�����̏W�ߕ��v��������̂ł��B�������č��E�̂����̓�������A��Ƃ̍�����c�����܂��B
���v�v�Z���̌���
���v�v�Z���́A��Ƃ��s�Ȃ����c�Ɗ����ɑ��Ăǂ̂悤�ȗ��v���p��������������\�����ނł��B���v�v�Z���́u���v�v�u��p�v�u���v�v��3�̗v�f���琬�藧���Ă��āA���ꂼ��ȉ��̂悤�ȈӖ�������܂��B
| ���v | �c�Ƃɂ���ē������� |
| ��p | ���v�邽�߂Ɏx���������� |
| ���v | ���v���p���獷�����������z |
�܂�A3�̗v�f�͈ȉ��̌v�Z�����藧���܂��B
���v �� ���v �\ ��p
�����āA3�̗v�f�ɂ��ׂ������ނ�����A�S����5�ɕ��ނ���܂��B
| ���㑍���v | ��Ƃ̖{�Ƃœ������v�B���㍂���猴���E�d����p���������������� |
| �c�Ɨ��v | ���㑍���v����L����`��E��ʊǗ������������������ |
| �o�험�v | �{�ƈȊO�̎��v����{�ƈȊO�̔�p�̍������c�Ɨ��v�ɑ��������́i�c�Ɨ��v�{�c�ƊO���v�[�c�ƊO��j |
| �ň��O���������v | �o�험�v�ɓ��ʑ��v�i�c�Ɗ����ȊO�ŗՎ��I�ɔ����������z�ȑ��v�j�𑫂������������� |
| ���������v | �ŏI�I�ȑ��v�i�ň��O���������v����ŋ������������́j |
�����5�̗v�f�͈ȉ��̂悤�ɋL����A�ォ�牺�Ɍ������Čv�Z�ł���悤�ɏ�����Ă��܂��B
| ���� | ���z |
| ���㍂ ���㌴�� | �������������~ �������������~ |
| ���㑍���v | �������������~ |
| �̔���E��ʊǗ��� | �������������~ |
| �c�Ɨ��v | �������������~ |
| �c�ƊO��p | �������������~ |
| �o�험�v | �������������~ |
| ���ʗ��v ���ʑ��v | �������������~ �������������~ |
| �ň��O���������v | �������������~ |
| �@�l�łȂ� | �������������~ |
| ���������v | �������������~ |
�L���b�V���t���[�v�Z���̌���
�L���b�V���t���[�v�Z���́A����ǂ̂悤�ɂ���������A�����̎c�����ǂꂭ�炢�Ȃ̂���\�������ނł��B�L���b�V���t���[�v�Z��������ƁA�茳�ɂ��邨���̐��m�ȋ��z��������܂��B�Ⴆ�A���オ�o���Ƃ��Ă��K�������茳�Ɏ���������Ƃ͌���܂���B�܂��A�d������s�Ȃ��Ă��A�������o�Ă����Ȃ����Ƃ�����܂��B���������͑��v�v�Z�������ł͕�����Ȃ��̂ŁA�L���b�V���t���[�v�Z�����쐬���Ė��炩�ɂ��܂��B
�L���b�V���t���[�v�Z���́u�c�Ɗ����v�u���������v�u���������v��3�̋敪�ɕ������A���ꂼ��ȉ��̈Ӗ�������܂��B
| �c�Ɗ��� | ��Ƃ̖{�Ƃɂ��c�Ɗ����Ő������L���b�V���̑��� |
| �������� | �����ɂ��L���b�V���̑��� |
| �������� | �������B�ɂ��L���b�V���̑��� |
�L���b�V���t���[��3�ɋ敪���āA�ȉ��̂悤�Ȃ������ō쐬����Ă��܂��B
| �c�Ɗ����ɂ��L���b�V���t���[ | |
| �ň��O���������v | �������������~ |
| �������p�� | �������������~ |
| ������̑��� | �������������~ |
| �d�����̑��� | �������������~ |
| �@�l�œ��̎x�� | �������������~ |
| �c�Ɗ����ɂ��L���b�V���t���[ | A |
| ���������ɂ��L���b�V���t���[ | |
| �L���،��̎擾 | �������������~ |
| �L���،��̔��p | �������������~ |
| �Œ莑�Y�̎擾 | �������������~ |
| �Œ莑�Y�̔��p | �������������~ |
| ���������ɂ��L���b�V���t���[ | B |
| ���������ɂ��L���b�V���t���[ | |
| �ؓ����̑��� | �������������~ |
| �ؓ����̕ԍ� | �������������~ |
| ���������ɂ��L���b�V���t���[ | C |
| ��������ь����������̑����z | A+B+C=D |
| ��������ь����������̊���c�� | F |
| ��������ь����������̊����c�� | D+ F |
���̂悤�ɁA�L���b�V���t���[�͏ォ�牺�Ɍ������ēǂނ��Ƃ��\�ł��B�u�c�Ɗ����v�u���������v�u���������v���ꂼ��̍��v�Ɋ���c���𑫂������̂��A�����c���ł��邱�Ƃ��ȒP�ɕ�����܂��B
���ቿ�i�ő����E�풓�\�Ȍo���A�E�g�\�[�V���O��
���Z���̏�����
���Z���̍쐬�͓���C���[�W�����邩������܂��A3�̃X�e�b�v�ŕ�����ƕ�����₷���ł��B
- ���Z�c�����m�肳����
- �ŋ��Ȃǂ̌v�Z���s���m�F����
- ���Z���̍쐬����
�܂����Z���������O�ɁA���Z�c�����m�肳���܂��傤�B����͎��ۂ̎c�������Z���Ƃ�����̊m��Ȗڂ̎c���ƈ�v���Ă��邱�Ƃ��m�F������̂ł��B�c������v���Ă��Ȃ��ꍇ�͂ǂ����ɋL���R�����z�̌�肪����ƍl�����܂��B
���ɁA�ŋ��Ȃǂ̌v�Z���s���܂��B�����Ń|�C���g�́A�͂��߂ɏ���ł��v�Z���A�Ō�ɖ@�l�ł��v�Z���邱�Ƃł��B����ł͉������ł��牼������ł����������Čv�Z���܂��B�������łƂ͔���ɂ���ėa����������ŁA��������ł͌o���d����Ŏx����������ł̂��Ƃł��B���̍��������������ƂŁA�x�����Ă��Ȃ�����ł��Z�o�ł��܂��B
�܂��A�@�l�ł́u�@�l�Z���Łv��u�@�l���ƐŁv�ȂǍׂ������ނ�����A���I�Ȓm�����K�v�ɂȂ�܂��B���̂��߁A��ʓI�ɂ͐ŗ��m�̂悤�Ȑ��ƂɈ˗����邱�Ƃ������ł��B
�������Ďc�������肵����A�ݎؑΏƕ\�A���v�v�Z���A�L���b�V���E�t���[�v�Z�����쐬���Ă����܂��B���Z���͈�ʓI�ɁA�ȉ��̂悤�ȃt���[�ō쐬����܂��B
- �o���S���҂����Z�����쐬����
- �o�c�҂��m�F����
- ������ŏ��F�����
- ���呍��Œ�o����
- ���呍��ŏ��F����
���Ȃ݂ɁA���Z���ɂ͍����O�\�ȊO�ɂ��ȉ��̂悤�ȏ��ނ�����܂��B
- ���厑�{���ϓ��v�Z��
- �ʒ��L�\
- ��������
- ���ƕ�
���ቿ�i�ő����E�풓�\�Ȍo���A�E�g�\�[�V���O��
�܂Ƃ�
���̋L���ł́A���Z���̌����⏑�����ɂ��ĉ�����Ă����܂����B���Z���Ƃ͍������\�̂��ƂŁA�ݎؑΏƕ\�A���v�v�Z���A�L���b�V���t���[�v�Z��������܂��B������ǂ݉������ƂŁA��Ђ̍�����Ԃ�N�Ԃ̉c�Ɨ��v�A�����̗�����m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B���Z���͌o���S���҂��쐬���邱�Ƃ������ł����A���m�����K�v�ȏ�ʂł͐ŗ��m�Ɉ˗����邱�Ƃ������ł��B���Z���̍쐬���K�v�Ȍo���S���҂́A��b�m����}���A���ƂɈ˗�����̂���������Ƃ����ł��傤�B
�������RSTANDARD�ł́A�o�����͂��߂Ƃ����v�A�Ŗ��A�l���̑�s�E�A�E�g�\�[�V���O�T�[�r�X����Ă���܂��B
�����ł̑Ή����\�ł���ƂƂ��ɁA�o���L�x�Ȑ��Ј����o���S���҂�ӔC�҂̘g����������ƃJ�o�[�������܂��B
�o���A�E�g�\�[�V���O�E��s�Ȃ瑦���E�ቿ�i��RSTANDARD�ւ��C�����������B
�o���A�E�g�\�[�V���O�ɂ��ďڂ����m�肽�����͈ȉ��̂������ߋL�������Ђ������������B
�������ߋL���F�o���A�E�g�\�[�V���O�Ƃ́H�����b�g�E�f�����b�g�ƋƎ҂̐������I�ѕ�
�o���A�E�g�\�[�V���O�Ɋւ���
�T�[�r�X�ڍׂ͂�����