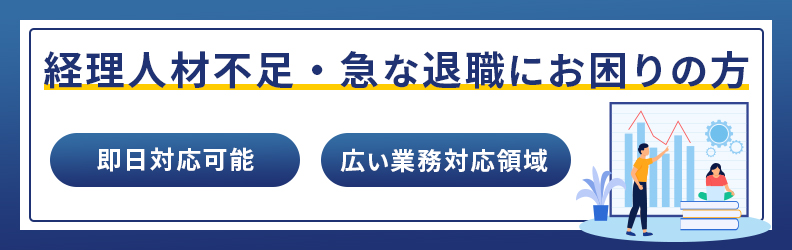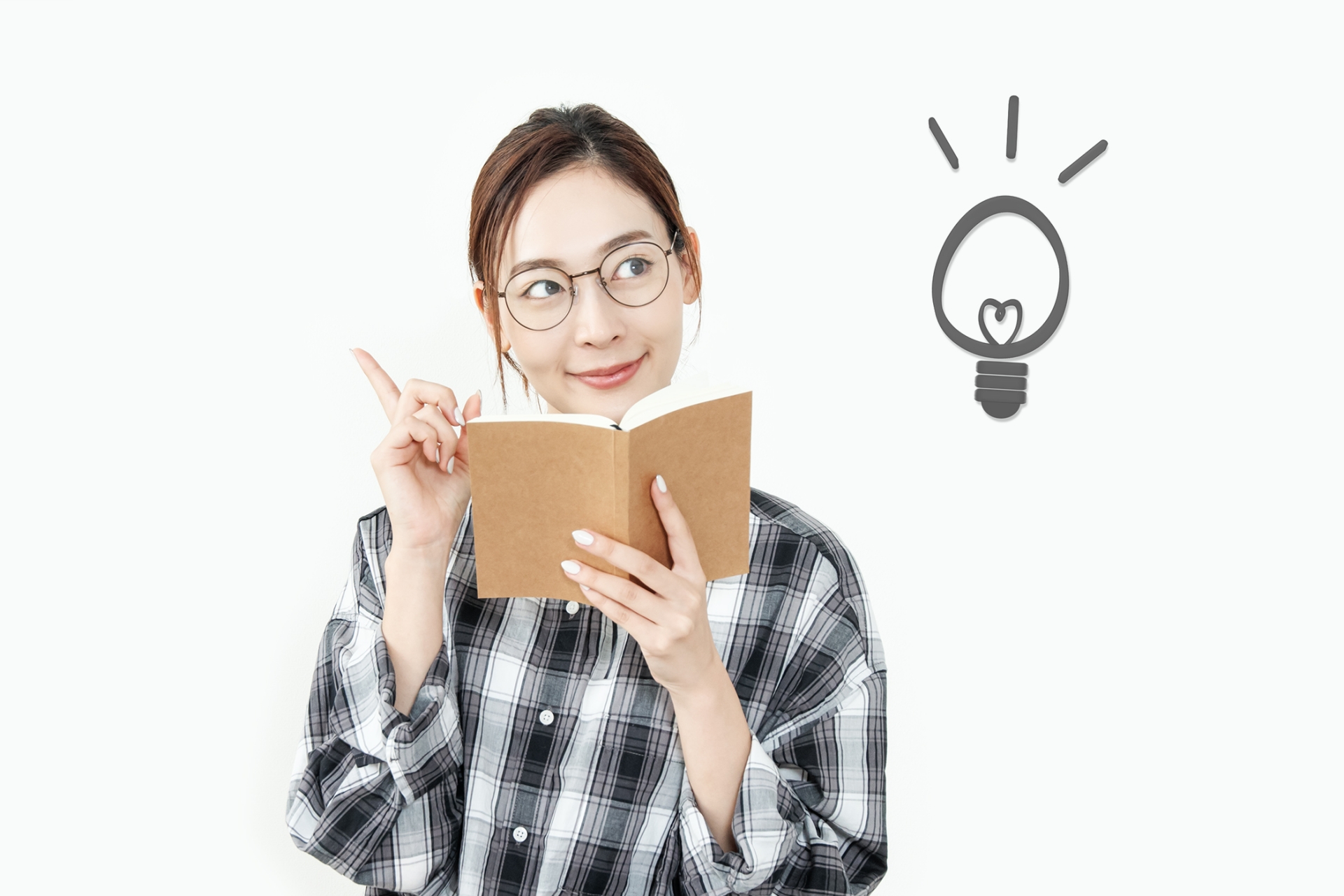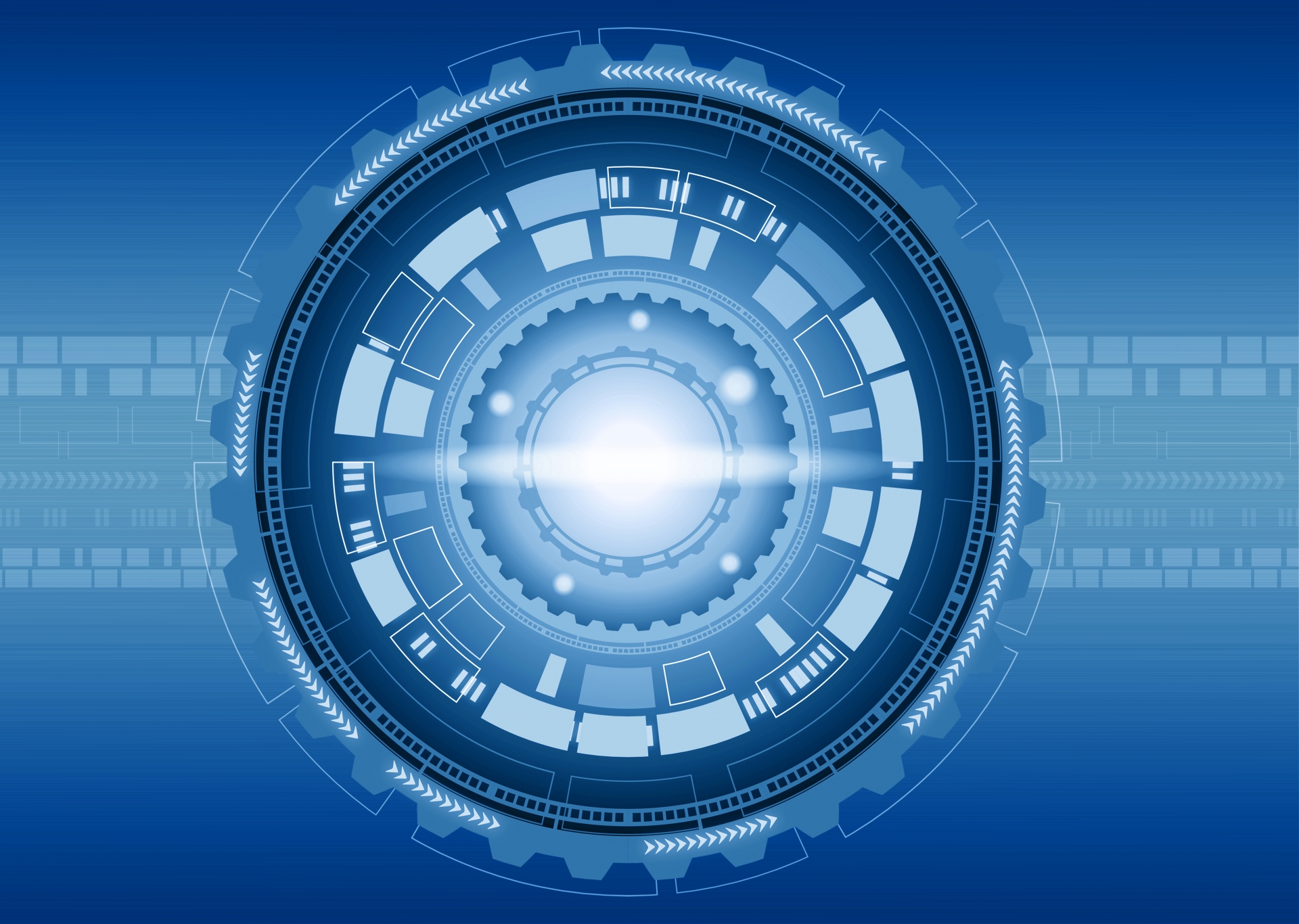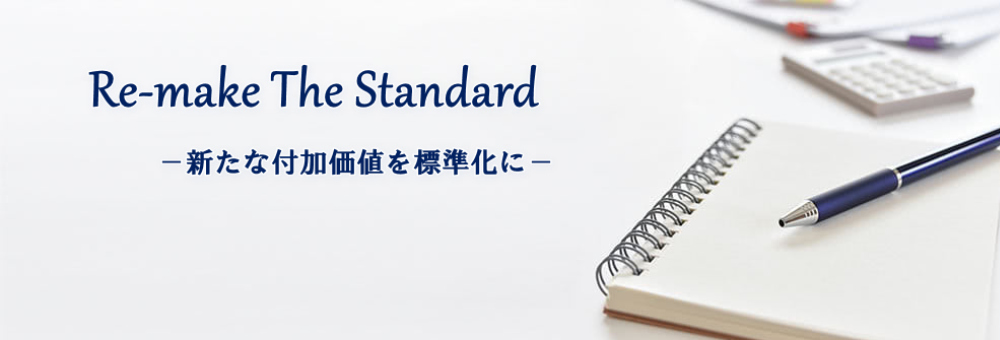
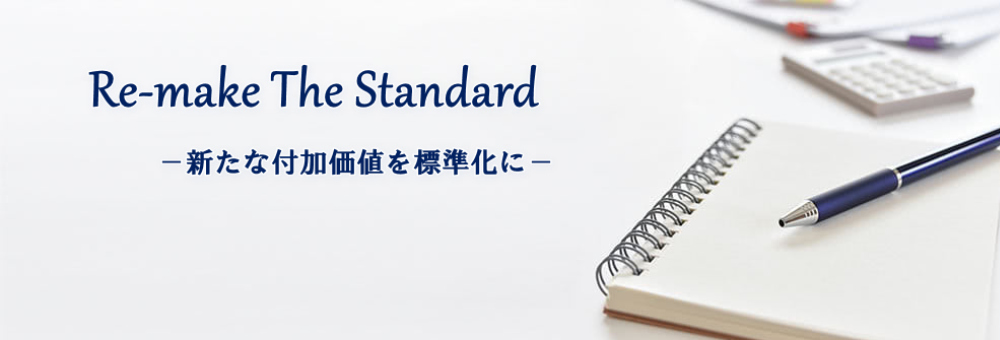
経営分析で使う固定費と変動費の違いとは?その区分方法や業種ごとの科目一覧を解説
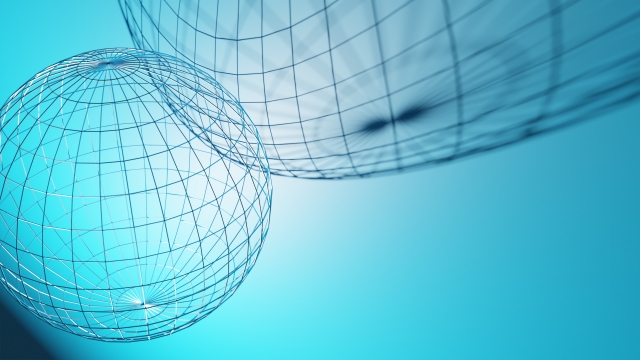

株式会社RSTANDARD
経理や人材育成などにおけるお役立ち情報を発信中。 押さえておきたい基本知識から役立つノウハウなどRSTANDARDならではの視点と情報量でお届けします。
「固定費」と「変動費」は、普段の経理業務での考え方とは少し違います。経営分析の考え方なので、携わったことのない方にとっては理解するのが難しいのではないでしょうか。
そこで、本記事では経営分析で必要な「固定費」「変動費」の計算方法について紹介します。また、業種ごとの勘定科目一覧とそれぞれの区分などについても概要をまとめました。
経費の把握は経営改善の第一歩です。ぜひ本記事を参考にして取り組んでみてください。
経理アウトソーシングで業務効率化・コスト削減
経理アウトソーシングならRSTANDARD
変動費と固定費の違い
経済分析・経営費管理をする際に、変動費と固定費の区分は非常に重要です。
変動費とは、一定の期間や条件によって金額が変動する費用のことです。
つまり、月々の支出が必ずしも一定ではなく、状況やニーズによって金額が変わる場合に変動費として分類されます。
一方、固定費は定期的に一定の金額が支払われる費用であり、月々の支出が一貫して同じ金額であることが特徴です。
変動費と固定費を適切に区別し、管理することで、予算立てや資金計画の策定がより効果的に行えます。
ここからは、変動費と固定費について、例を交えながらそれぞれ解説していきます。
固定費とは
固定費とは売上高などに関係なく、常に一定の期間で発生する費用のことを指します。
言い換えると「事業活動を維持・継続するための費用」です。
建物・設備などが稼働していなくても経費が発生することから「不変費」とも呼ばれます。
該当するのは、売上(製造)原価・販売費および一般管理費・営業外費用の一部です。
そのため、固定費率が高くなると、売上の減少が経営を圧迫する可能性があります。
また、損益分岐点の売上高も高くなりやすいので、コストカットする際は最初に削減を考える項目です。
固定費の例
ここからは、実際の「固定費」の例を見ていきましょう。
ここでは、以下の8項目について、簡単に解説していきます。
- 人件費:従業員に渡す給与・各種手当・福利厚生費など
- 減価償却費:固定資産の購入額を耐用年数に合わせて分割した費用
- 地代家賃:借りている土地と建物の賃料
- 光熱費:電気やガスなどのエネルギーを使うためにかかる費用
- 保険料:保障を得る対価として保険会社に支払う火災保険費用など
- リース料:毎月一定のリース料金をリース会社に支払う均等月払いのこと
- 広告宣伝費:消費者に対して自社の製品やサービスを告知するために使う費用
- 支払利息:銀行などの金融機関や取引先からの借入金などについて支払う利息
毎月ある程度決まった金額を支払う必要のある経費が該当します。
なお、計算が複雑で迷いがちな減価償却については、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、ご覧ください。
「関連記事>>減価償却とは?計算方法やメリット・耐用年数
変動費とは
変動費とは、毎月の売上高(販売量)や生産量に比例して増減する経費のことです。
小売・卸業であれば商品の仕入高、製造業などであれば材料の仕入高や梱包費、配送運賃、梱包材の費用や燃料費、倉庫管理を外部に委託している場合であれば、外注委託費などが変動費の代表例となります。
代表例としてあげられた勘定科目を見るとわかるように、売上高・販売高、生産高などが多くなればその分計上される費用も多くなり、少なくなれば計上される経費もその分減少するのが特徴です。
そのため、変動費は「可変費」とも呼ばれます。
変動費の例
次に、実際の「変動費」の例を確認していきましょう。
ここで紹介する例は、以下の8項目です。
- 人件費:従業員に渡す賞与や残業代など
- 原材料・商品の仕入:販売目的の商品や原材料の購入費用
- 梱包材費:商品を発送するなどに使用する梱包資材費用
- 運送費:商品を販売した際に必要な運賃
- 燃料費: 電気事業者が電気をつくるための原材料費用
- 外注費:自社事業の一部を外部委託し、請負契約を締結した結果支払う費用
売上や生産高などに連動して変わるのが、「変動費」となります。
固定費・変動費の計算方法
後で説明する限界利益や損益分岐点の算定を適切に行うためには、固定費・変動費を把握して計算することが必要です。ただし、固定費の中には、変動費が含まれていることもあります。
固定費と変動費の算定基準としては、売上もしくは生産ごとに発生する、もしくは一定頻度で固定的に発生するかが主なものです。
たとえば、広告宣伝費であれば単発的なものは変動費として、毎月固定的にかかるものは固定費で計算します。地代家賃であれば歩合で支払う部分を変動費となり、定額部分は固定費というのが基準となります。
明確に分けられない場合は、前年度の割合を算定して計算するのもひとつの方法です。
▽低価格で即日・常駐可能な経理アウトソーシング▽
業種別の固定費・変動費の一覧
ここでは、業種ごとにわかれる固定費と変動費分類の考え方を紹介します。
【製造業】
●固定費
(製造原価)
- 直接労務費
- 間接労務費
- 福利厚生費
- 減価償却費
- 地代家賃
- 保険料
- 修繕費
- 旅費交通費
- その他製造経費
(販売費および一般管理費など)
- 人件費
- 通信費
- 支払運賃
- 荷造費
- 広告宣伝費
- 接待交際費
- 支払利息
- 割引料
- 従業員の教育費
- 租税公課
- 研究開発費
- その他販売費・管理費
●変動費
- 直接材料費
- 間接材料費
- 買入部品費
- 外注費
- 重油等の燃料費
- 陶器製品仕入原価
- 期首製品棚卸高
- 期末製品棚卸高
- 酒税
【卸・小売業】
固定費
- 人件費
- 旅費交通費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 車両燃料費(※)
- 車両修理費(※)
- 保険料(※)
- 減価償却費
- 接待交際費
- 補償費
- 修繕費
- 支払利息
- 割引料
- 水道光熱費
- 租税公課
- 従業員教育費
- その他販売費・一般管理費
●変動費
- 売上原価(当期商品仕入高、期首期末商品棚卸高)
- 支払運賃
- 支払荷造費
- 支払保管料
- 車両燃料費(※)
- 保険料(※)
(※)車両燃料費・保険料については、卸売業ではそれぞれ半分ずつ計上します。車両修理費は固定費のみ半分計上してください。
(※)小売業については、全額固定費となります。
【建設業】
●固定費
- 人件費
- 労務管理費
- 租税公課
- 地代家賃
- 保険料
- 事務用品費
- 交通費
- 接待交際費
- 補償費
- 修繕維持費
- 広告宣伝費
- 支払利息
- 割引料
- 減価償却費
- 動力・用水・光熱費(一般管理費のみ)
- 従業員教育費
- その他経費・管理費
●変動費
- 材料費
- 労務費
- 外注費
- 仮説経費
- 動力・用水・光熱費(完成工事原価のみ)
- 運搬費
- 機械等経費
- 設計費
参照元:中小企業BCP策定運用指針(https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_05c_4_3.html)
上記の勘定科目は、あくまでも一例です。固定費・変動費の区別基準は、それぞれで異なるので、事業の実態に合わせて振り分けを行ってください。
変動費と固定費を分ける方法
経営上の意思決定を行うために必要なのが、事業活動において発生した経費などを、さらに変動費・固定費へ分けていく作業(固変分解)です。
ここでは、固変分解とは何かというところから、その区別方法について説明します。
固変分解とは
企業活動において発生した経費を、変動費と固定費に区別することを固変分解、売上(製造)原価について固変分解することを原価分解といいます。
固定費・変動費の意味、それぞれの代表例については最初に説明したとおりです。しかし、固変分解を行う際の絶対的な区別基準がないため、すべての経費について正確に分けることはできません。
たとえば、水道光熱費は一般的なオフィスなどであれば固定費に分類されます。しかし、来店客や稼働状況によって変動することが予測される場合は、違う方法で区分することもあるでしょう。
固変分解する際に使われる手法は、「勘定科目法」と「回帰分析法」という2つです。以下で、その手法について詳しく解説します。
勘定科目法とは
勘定科目法は、企業会計の実務において固変分解を行う際に、もっとも使われる手法となります。
その名前のとおり、勘定科目ごとに変動費に該当するか、固定費に該当するかを一つひとつ判断する手法です。ただし、先にも紹介したとおり、変動費になるか固定費になるかは、業種もしくはその発生理由によって異なります。
たとえば、人件費の場合であれば、固定給や法定福利費などは毎月固定的に出るので固定費です。しかし、繁忙期に臨時雇用したアルバイト・派遣社員の給料、インセンティブに応じて支給される賞与は変動費になります。
迷った場合は、その発生理由もしくはどちらの性質が強いか、過去の実績を参考にするなどして按分割合を決めるといいでしょう。
関連記事>>勘定科目とは?科目一覧を詳しく解説
回帰分析法とは
回帰分析法とは、売上高と総費用を散布図に当てはめて固変分解を行う方法です。
まずは会計年度の売上と経費の表を用意してください。次に縦軸を「費用」、横軸を「売上高」としたグラフを用意して、それぞれの月ごとに売上高とかかった経費(費用)の交点に点を打ちましょう(おおよそで大丈夫です)。
その後、打った12個の点から大幅に外れないようにグラフを書いていきます。そのグラフの傾きが変動費率、切片が固定費となります。なお、手作業でやるのは手間がかかるので、Excelを使って行うと簡単に分析可能です。
先にも書いたように、実務上では勘定科目法を用いる企業が多いですが、より正確な分析を求める場合、回帰分析法を使う企業もあります。
固定費と変動費から分かる2つの指標
企業の費用構造を把握するためには、固定費と変動費の比率を計算することが重要です。
生産量や販売量にかかわらず一定の金額が発生する「固定費」と生産量や販売量に応じて変動する「変動費」の比率を計算することで、企業のコスト構造がどれだけ固定費に依存しているかを把握できます。
この指標は、企業の利益やキャッシュフローの予測、またコスト削減や価格設定の戦略立案において重要な情報となります。
事業活動において利益を出すためにも、必ず押さえておかなければなりません。
ここでは、変動費と固定費をきちんと把握することでわかる以下4つの指標について解説していきます。
- 限界利益
- 損益分岐点
- 安全余裕率
- 売上高変動比率
それぞれの意味と使用する目的について説明していきます。
限界利益とは
限界利益とは、下記の算式で表される数字のことです。
算式:売上高−変動費=限界利益
限界利益から売上高を割ると、限界利益率がわかります。
限界利益・限界利益率は、売上高の増加に伴う利益の増加分がわかる指標です。
たとえば主力製品A・Bそれぞれの売上高が1万円・1.5万円、把握している変動費が同じく4,000円・4,500円とします。それぞれの限界利益と限界利益率は下記のとおりです。
- A 限界利益:6,000円 限界利益率:60.0%
- B:限界利益:10,500円 限界利益率:70.0%
ここから、限界利益と限界利益率が高い製品(商品)の販売に注力することで、利益を上げられることがわかります。
損益分岐点とは
損益分岐点とは、「売上高−費用(変動費+固定費)=0」になるポイントのことです。この損益分岐点売上高は、下記の算式で求められます。
算式:固定費÷限界利益率=損益分岐点売上高
(例) 固定費2,000円、限界利益率40%
上記の算式に当てはめると、2,000円÷40%=5,000円です。したがって、上記の例では5,000円が損益分岐点売上高です。
グラフを作る際は、縦軸を総費用、横軸を売上高にして、固定費を表す直線と総費用線(固定費+変動費)、売上高のグラフを書きます。
売上高と総費用線が交わる点を超えると利益になる仕組みです。
ただし、固定費が高いと損益分岐点も右側に移動します。そのため、多くの売上を出せなければ赤字になるので注意が必要です。
安全余裕率とは
安全余裕率は、現在の売上高が損益分岐点をどの程度上回っているかを示す数値です。
これは経営の安全性を評価するための財務指標であり、売上が何%減少すれば赤字になるのか、または売上を何%伸ばせば黒字にできるのかを示します。
安全余裕率の計算式は以下の通りです。
- 安全余裕率(%)=(売上高−損益分岐点売上高)÷売上高×100
この計算によって、経営における余裕の程度を把握できます。
安全余裕率が高いほど、企業の経営は安定しており、安全性が高いといえるでしょう。
一方で、安全余裕率が低い場合は、経営が危うい状況にあることを示しています。
以上のように、安全余裕率は企業の経営状態を評価するうえで重要な指標であり、経営者はこの数値を把握し、適切な経営戦略を構築する必要があります。
安全余裕率を高めるためには、販売促進やコスト削減などの施策を検討し、損益分岐点をできる限り上げることが求められます。
売上高変動比率とは
売上高変動比率は、変動費を売上高で割ったものです(式:変動費÷売上高)。
変動費とは、生産量や販売量に応じて変動する費用のことで、企業の活動に伴い売上高に比例して増えます。
具体的には、材料費や販売手数料、商品の運送費などが挙げられます。
変動費率は、売上高に対する変動費の比率を示します。
この比率を求めることで、企業の費用構造がどれだけ変動費に依存しているかを把握することができるのです。
売上高変動比率が高い場合、企業の費用が売上高によって大きく変動することを示しています。
一方、売上高変動比率が低い場合は、企業の費用が比較的安定していることを示しており、この指標は、企業が売上高の変動に対応するための財務戦略を立てるうえで重要な情報となります。
たとえば、売上高変動比率が高い場合は、需要変動に柔軟に対応するためのコスト削減策やリスク管理が必要となるでしょう。
固定費と変動費の削減方法
固定費の削減方法には、下記のようなものがあります。
- オフィスにかかる賃料の見直し
- 業務全体をシステム化する
- アウトソーシングの活用
- 会計・請求システムなどの見直し
経費を見直す際は、割合の多いところから手をつけるのが鉄則です。人件費や地代家賃の削減から考えてみてください。
変動費の場合であれば、次のようなことが考えられます。
- 安い外注先に変更する
- 仕入れ価格の交渉をする
- ペーパーレス化による消耗品の削減
- 製造工程の見直し
大きな割合を占めるのは仕入れ価格ですが、無理な交渉をすると製品やサービスの質の低下につながります。できれば、それらに影響のない部分で削減することを考えましょう。
▽低価格で即日・常駐可能な経理アウトソーシング▽
2つの指標をしっかり理解して経営に活かそう
本記事では、経理業務の中でよく用いられる「変動費」と「固定費」の意味と区別方法、限界利益と損益分岐点について解説してきました。いかがでしたでしょうか。
経費を適切に把握することで的確な意思決定ができます。ただし、その基準は業種・それぞれの性質などによっても異なるので、しっかりと分析して適切に計上することが必要です。
また、基準は絶対的なものではありません。新しい経費が発生すると変わるので、定期的に見直してください。
2つの指標は、企業がより利益を生み出しやすい環境を作るためにも重要な指標です。これらの指標が表す意味をしっかりと理解して、利益構造の強化と強い企業体質の構築に取り組みましょう。
株式会社RSTANDARDでは、経理をはじめとする会計、税務、人事の代行・アウトソーシングサービスを提供しております。
即日での対応が可能であるとともに、経験豊富な正社員が経理担当者や責任者の枠をしっかりとカバーいたします。
経理アウトソーシング・代行なら即日・低価格のRSTANDARDへお任せください。
経理アウトソーシングについて詳しく知りたい方は以下のおすすめ記事をぜひご覧ください。
おすすめ記事:経理アウトソーシングとは?メリット・デメリットと業者の正しい選び方