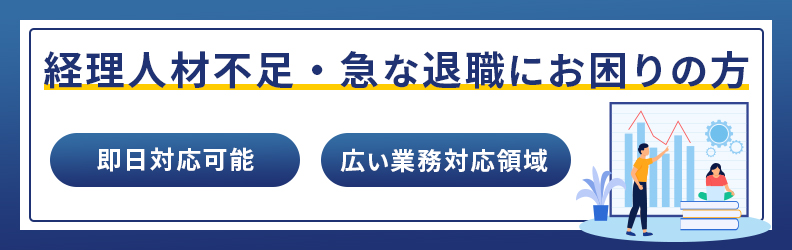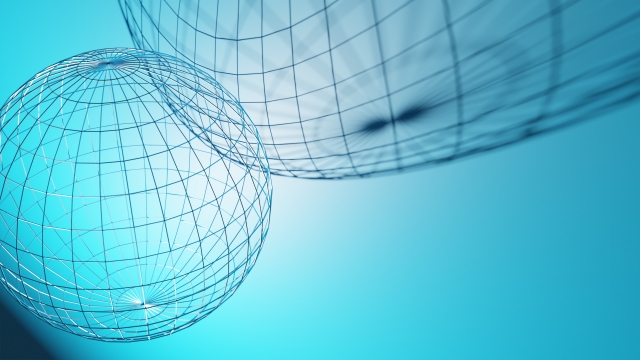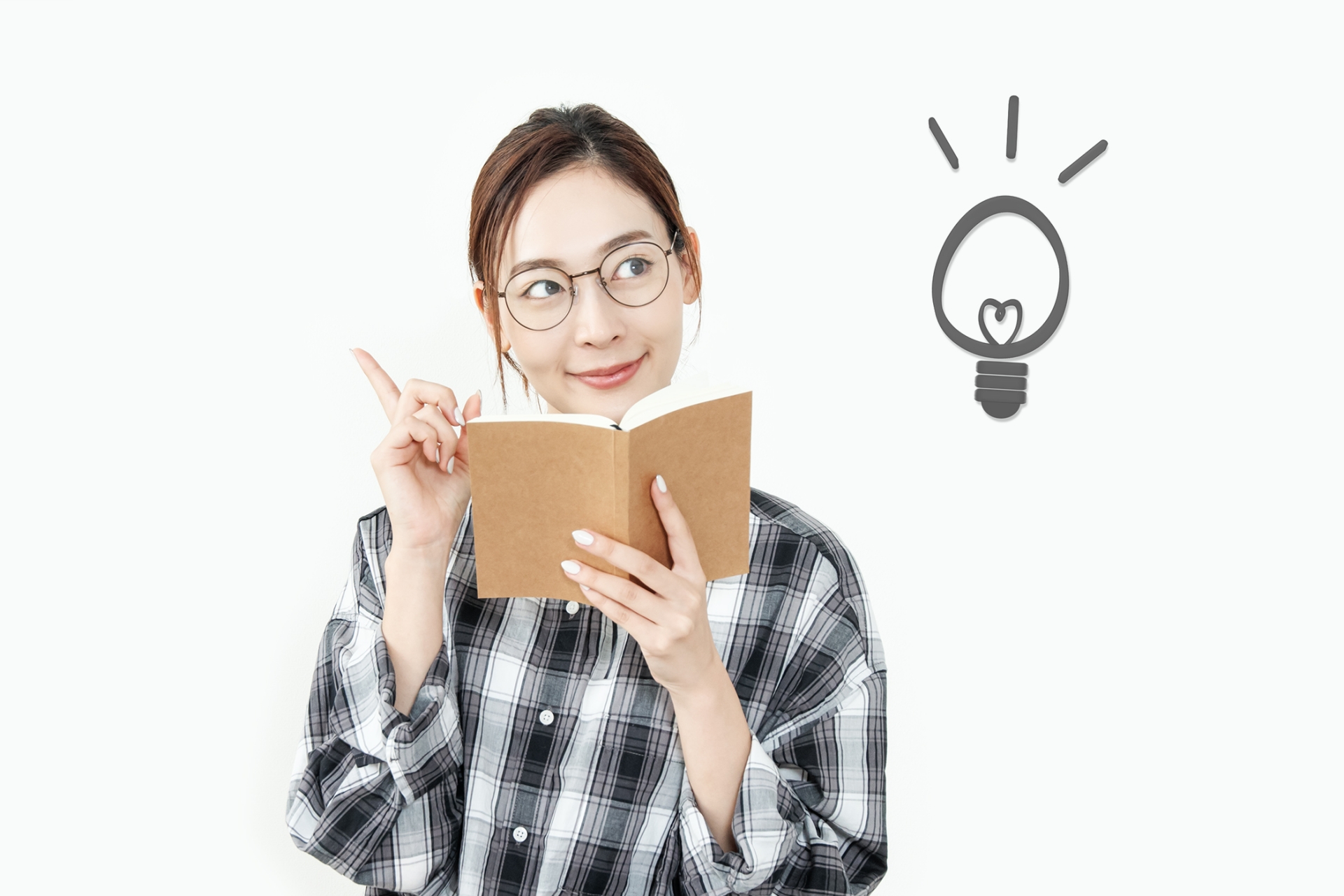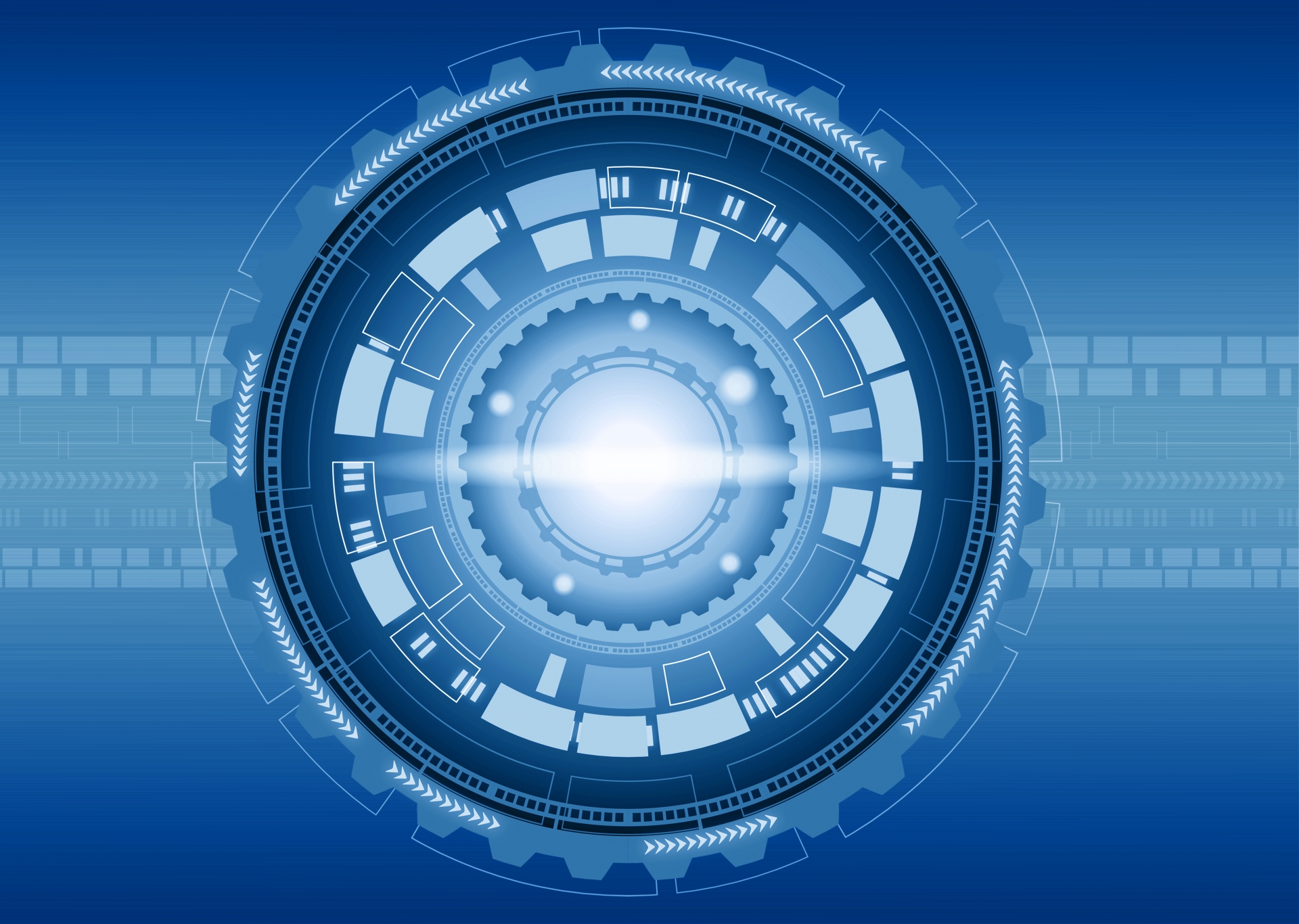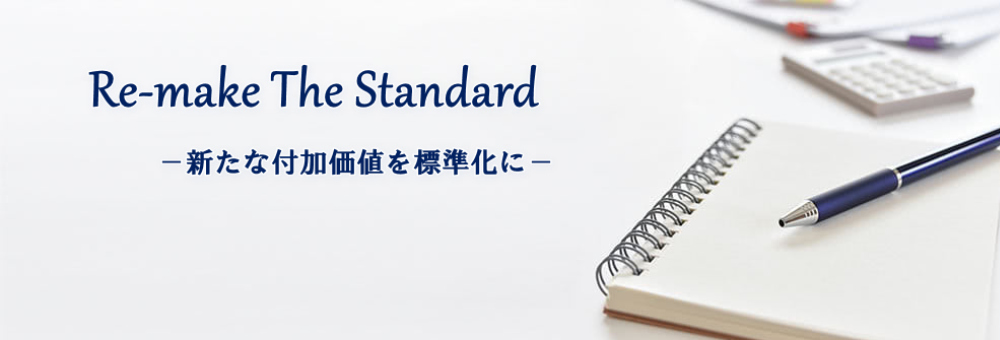
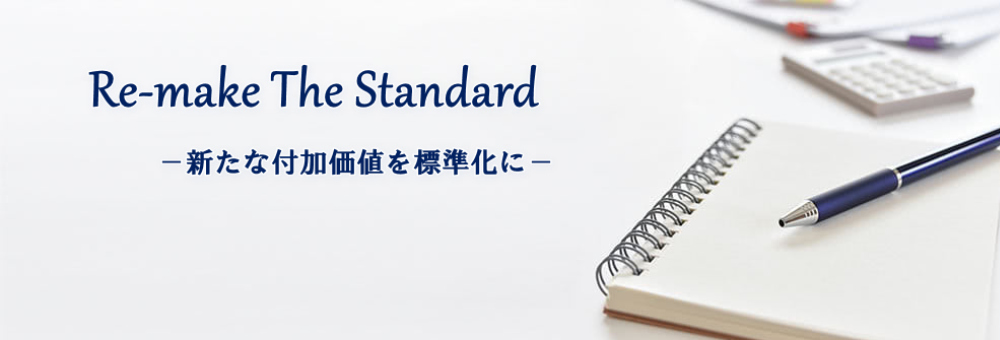
�N��������s�Ƃ́H��ȃT�[�r�X���e�Ɣ�p�̑�����Љ�


�������RSTANDARD
�o����l�ވ琬�Ȃǂɂ����邨�𗧂����M���B �������Ă���������{�m������𗧂m�E�n�E�Ȃ�RSTANDARD�Ȃ�ł͂̎��_�Ə��ʂł��͂����܂��B
�N�������Ɋւ���Ɩ��́A1�~����Ƃ��~�X�ł��Ȃ��A����d�v�Ȏd���ł��B
�o������l�����̕��ɂƂ��āA�N���������s�������͓��ɖZ�����ł���ˁB
�����Ŗ{�L���ł́A�N�������̋Ɩ��̕��S���y���ł���N��������s�̃T�[�r�X���e���p�̑�����Љ�܂��B
�N�������Ɋ֘A����Ɩ��̕��S���y�����������́A���ЎQ�l�ɂ��Ă��������B
�o���A�E�g�\�[�V���O�ŋƖ��������E�R�X�g�팸
�o���A�E�g�\�[�V���O�Ȃ�RSTANDARD
- �N�������Ƃ�
- �N��������s�Ƃ�
- �N��������s�̃����b�g
- �N��������s�̃f�����b�g
- �N��������s���g���ꍇ�̗���
- �N��������s�𗘗p����ۂ̒��ӓ_
- �N��������s��3�̈˗���
- �N��������s��Ђ̔�p�̖ڈ�
- �L����s�Ƃ́H�Ɩ����e����b�g�E��p����
- �o���A�E�g�\�[�V���O�Ȃ瑦���E�풓�\��RSTANDARD��
- �N��������s�𗘗p���邱�ƂŔN�������ɂ������Ƃ̕��S�����炷���Ƃ��ł���
�N�������Ƃ�
�N�������́A�����̋�����{�[�i�X���獷�������ꂽ�����ł��A�x�����ׂ������������łƏƍ����Ă��̍����������Ƃ̂��Ƃł��B
��Ј��̏ꍇ�A�������疈�������ł�����������Ă��܂��B
�������A���̍��������ꂽ�����ł͐������[�Ŋz�ł͂Ȃ��̂ł��B
���ۂɎx�������[�Ŋz�Ɛ����������ł��ƍ����邱�ƂŐ������[�Ŋz���킩��̂ŁA�����߂��Ă���������߂�A�s�����Ă���悤�ł���Ύx�����K�v������܂��B
�x�����ׂ������������ł��v�Z���A�덷����������̕ԋ���lj��̎x�������m�肳���邱�Ƃ��N�������ł��B
�������[�Ŋz�̌v�Z���@
�܂��A�������[�Ŋz�̌v�Z���邽�߂ɔN�Ԏ����z�E�Љ�ی����E�����Ŋz��3���W�v���܂��B
���ɔN�Ԏ����z����A���^�����T���z�������A���^�����z���v�Z���܂��B
���^�����T���z�͔N�Ԏ����z�ɂ���ĕϓ����邽�߁A���L�̕\���Q�l�ɂ��Ă��������B
| �N�Ԏ����z | ���^�����T���z |
| 180���~�ȉ� | 180���~�ȉ� �������z�~40��-10���~ 55���~�ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A55���~ |
| 180���~���@360���~�ȉ� | �������z�~30��+8���~ |
| 360���~���@660���~�ȉ� | �������z�~20��+44���~ |
| 660���~���@850���~�ȉ� | �������z�~10��+110���~ |
| 850���~�� | 195���~�i����j |
�y�Q�l�z���Œ��@No1410 ���^�����T��
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm?_fsi=P0RWd7o6
���^�����z���v�Z�ł������Ƃ́A���^�����z����]�ƈ�����\���̂����������T���z�������A�ېŏ������Z�o���܂��B
�����āA�N�������Ŋz���v�Z���܂��傤�B
�ېŏ����ɏ����ŗ����悶�āA��������T���z�������ƁA1�N�Ԃ̏����Ŋz���Z�o�ł��܂��B
| �ېŏ��� | �ŗ� | �T���z |
| 195���~�ȉ� | 5�� | 0�~ |
| 195���~��?330���~�ȉ� | 10% | 97,500�~ |
| 330���~��?695���~�ȉ� | 20�� | 427,500�~ |
| 695���~��?900���~�ȉ� | 23�� | 636,000�~ |
| 900���~��?1,800���~�ȉ� | 33�� | 1,536,000�~ |
| 1,800���~��4,000���~�ȉ� | 40�� | 2,796,000�~ |
| 4,000���~�� | 45�� | 4,796,000�~ |
�y�Q�l�z���Œ��@No.2260?�����ł̐ŗ�
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
�����Ŋz����Z��[���T�������������z���A�N�������Ŋz�ł��B
�Ō�ɔN�������Ŋz�ɕ������ʏ����ł��܂ފ����ł���102.1���������āA�N���N�Ŋz���v�Z���܂��B
�N���N�Ŋz�ƌ������������Ŋz���ׁA�N���N�Ŋz�������Ŋz��菭�Ȃ��ꍇ�ɂ͑����x���������̋��z���ҕt���Ƃ��Ė߂�܂��B
�t�ɁA�N���N�Ŋz�������z���������ꍇ�́A�{���x�����ׂ��ŋ����x�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��̂ŁA�lj��Œ��������Ƃ����d�g�݂ł��B
�N��������s�Ƃ�
12���̔ɖZ���̋Ɩ����������I�ɍs�����߂ɁA�N��������s�����p�����Ƃ�����܂��B
�N��������s�Ƃ́A�N�������̋Ɩ����O���̉�ЂɈϑ��ł���T�[�r�X�ł��B
�N���������s���ہA�Z���Ō����ł�Z���ŁA�ٗp�ی��ȂǁA���܂��܂Ȑ��m�����K�v�ł��B
�m���̂Ȃ��l���N���������s�����ƂŃ~�X���������邱�Ƃ�A���Ԃ𑽂��v���郊�X�N������܂��B
�N��������s�͂����������X�N��h�~���邽�߁A���ЂɔN�������Ɋւ�����I�Ȓm�����������l�ނ����Ȃ��ꍇ�ɁA�悭���p����邱�Ƃ������T�[�r�X�ł��B
�ŗ��m��ИJ�m�A�o����s�T�[�r�X���s����ЂȂǂ��A�N�������ƈꏏ�ɋ��^�v�Z�̋Ɩ����ꊇ���Đ����������Ƃ������ł��B
�lj��ŗ������Ɩ@�蒲�����v�\�̍쐬��d�q�\���Ȃǂ̂�蕝�L���Ɩ����ϑ��ł���N��������s��Ђ���������܂��B
�N��������s�̃����b�g
�����͂�����̂̔N��������s�𗘗p����ׂ����킩��Ȃ��Ɗ����Ă����������ł��傤�B
���̃T�[�r�X�ɂ́A�R�X�g�̍팸�E�S���҂̕��S�y���E�~�X�̌����Ȃǂ̃����b�g������܂��B
���ЂɂƂ��ėL�v�Ɗ�����ꍇ�͗��p���Ă݂Ă͂������ł��傤���B�N��������s�̃����b�g���ڂ���������܂��B
�R�X�g�̍팸
�T�[�r�X�𗘗p���邱�ƂŃR�X�g�̍팸�ɂȂ���\��������܂��B
�c�Ƒ��lj��ō̗p����l���̐l�����}�����邩��ł��B
�N�������Ɩ��́A��ɐ\�������ނ̔z�t�E����A�N�������̌v�Z�A�@�蒲���̍쐬�Ɛ\���ō\������܂��B
�����̋Ɩ����A�����Ɩ��⌎���Ɩ��Ȃǂƕ��s���čs��Ȃ���Ȃ�܂���B
�ꎞ�I�ɋƖ��ʂ������邽�߁A�l��������鋰�ꂪ����܂��B
�N��������s�𗘗p����Ɛl�����}�����邽�߁A���p���������������Ƃ��Ă��R�X�g�̍팸�ɂȂ��邱�Ƃ�����̂ł��B
�o���S���҂̕��S�y��
�O�q�̒ʂ�A�N���������Ԃ͌o���S���҂̋Ɩ��ʂ��ꎞ�I�ɑ����܂��B
�������ɂ��ׂĂ̋Ɩ������������Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A�o���S���҂ɑ傫�ȕ��S�������邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B
�L���p�I�[�o�[�ɂȂ�ƁA�Ɩ������͒ቺ���邤���~�X���N����₷���Ȃ�܂��B
�o���S���҂ɂƂ��Ă���ЂɂƂ��Ă��]�܂�����ԂƂ͂����Ȃ��ł��傤�B
�N��������s�𗘗p����A�o���S���҂ɂ����镉�S�����点�܂��B�p�t�H�[�}���X�̒ቺ��h����_�����p���郁���b�g�ł��B
�֘A�L���F�o���~�X�͂Ȃ��N����H5�̌����ƌl�E�g�D���x���łł���Ώ��@
�~�X�̌���
���Ђōs�������~�X��h���₷���_���������܂���B
���Ђ̃X�^�b�t�ɔN��������C���Ă���ƁA���X�̋Ɩ��ɒǂ��Ė@�����Ȃǂ̏��������Ƃ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B
�N��������s����Ă����Ђ́A���̋Ɩ��̐��Ƃł��邽�ߖ@�����ȂǂɓK�ɑΉ����Ă��܂��B
�������A�v�Z�Ȃǂ̍�Ƃ����m�ł��B�R�X�g��Ɩ��̕��S��}���A���m�ɔN�������Ɩ���������������_�����͂Ƃ�����ł��傤�B
�֘A�L�������o���Ɩ���������������@����b�g
���ቿ�i�ő����E�풓�\�Ȍo���A�E�g�\�[�V���O��
�N��������s�̃f�����b�g
���p�ɂ�����C��t�������f�����b�g������܂��B��\�I�ȃf�����b�g�Ƃ�����̂��A�m�E�n�E��~�ςł��Ȃ��E�����ɂȂ�P�[�X������E�O���ϑ����ɂ����Ɩ�������Ȃǂł��B
�N��������s�̃f�����b�g���ڂ���������܂��B
�Г��Ƀm�E�n�E��~�ςł��Ȃ�
�O���̋Ǝ҂ɋƖ����ϑ����邽�߁A�Г��Ƀm�E�n�E��~�ςł��܂���B
�P�[�X�ɂ���Ă͔N��������s�T�[�r�X�𗘗p���Ȃ��ƁA�Ɩ��̐i�ߕ����킩��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����ł��傤�B
���ЂɃm�E�n�E��~�ς������ꍇ�́A�O������Ɩ��͈̔͂����肷��Ƃ悢��������܂���B
�d�v���̍����Ɩ������Ђōs�����Ƃɂ��A���S�����炵�m�E�n�E��~�ςł��܂��B
����ʂɂ���Ă͊����ɂȂ�\��������
��ʓI�ɃR�X�g���팸�ł���Ƃ����Ă���N��������s�ł����A���p����T�[�r�X�◘�p��������ɂ���Ă͎��ЂőΉ�������������ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B
�����ɂȂ�����͂��܂��܂ł����A����ʂ����Ȃ���1��������̒P���͊�{�I�ɍ����Ȃ�܂��B���p�O�ɃR�X�g���m�F���Ă������Ƃ��d�v�ł��B
�O���ϑ�������Ɩ�������
�֘A���邷�ׂĂ̋Ɩ����O���ϑ����邱�Ƃ͓���_�ɂ����ӂ��K�v�ł��B
�ꕔ�̋Ɩ��͎��ЂŎ��{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��P�[�X�����Ȃ�����܂���B
�Ⴆ�A�\�������ނ̔z�t�E����͎��Ђōs��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������ł��傤�B
�܂��A���ׂĂ̋Ɩ����˗��ł���ꍇ���A�]�ƈ��Ɋւ�����̂������܂ނ��߈ϑ�����Ɩ��͈̔͂�T�d�Ɍ��ɂ߂Ȃ���Ȃ�܂���B
�N��������s���g���ꍇ�̗���
�N��������s���g���ꍇ�̗�����m�F���Ă����܂��傤�B
�N��������s�́A���3�̃X�e�b�v������܂��B
�X�e�b�v�@�K�v�Ȏ����̊m�F������
�N��������s���˗�����ɂ́A���Ђŏ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����������܂��B
��s���Ă��炤��Ƒ�����ǂ̂悤�Ȏ������K�v�������Ă��炦�܂����A���Ђł���������c�����Ă����ƔN���������X���[�Y�ɍs����ł��傤�B
�N���������s�����߂ɕK�v�Ȏ����͈ȉ��ɂȂ�܂��B
�N��������s���˗�����ۂɕK�v�Ȏ���
- ���^�����҂̕ی����T���̐\��
- �����ی����T���ؖ����Ȃǂ̏ڍׂ��킩�鏑��
- �}�{�T�����i�ٓ��j�\����
- ���^�����҂̊�b�T���\�����A�������z�����T���\�����i���p�l���j
- ���^�����҂́i���葝���z���j�Z��ؓ��������ʍT���\�����A�ؓ����̔N���c�����ؖ����i�c���ؖ����j
���O�ɏ]�ƈ��ɘA��������5��ނ̏��ނ��������Ă��炢�A�N��������s��Ђɒ�o���܂��傤�B
��o�̕��@�͎�n����X���Ȃǂ�����A�N��������s��Ђɂ���Ă͒�o���@���w�肳��Ă���ꍇ������܂��B
�����A�N��������s��Ђɒ�o���������ɕs���▢��o�̎������������ꍇ�́A�Ē�o�̈˗������܂��B
�X�e�b�v�A�e��T���z�ƌ��������̌v�Z������
��o���������̊m�F��N��������s��Ђōs���A���Ȃ���f�[�^���͂�t�@�C�����O�����Ă��炢�܂��B
�����āA�e��T���z�ƔN�Ԃ̌����ł��v�Z���A�N�Ԃ̋��^�Ƃ̍��z���o���Ă��炤���Ƃ���{�I�ȗ���ł��B
�N��������s��Ђɂ���đΉ����Ă����T�[�r�X�̕����قȂ�܂��B
�N�������̂��ׂĂ̋Ɩ������Ȃ��Ă����ꍇ������A�\�����`�F�b�N��e�[�^���́A�t�@�C�����O�݂̂Ƃ������悤�ɁA�����I�ȑ�s�T�[�r�X���s���Ă����Ђ�����܂��B
���ׂĂ̋Ɩ����ϑ����邩�A�����I�Ɉϑ����邩�A���Ђŕ�����l�ނ��L����m����R�X�g�Ȃǂ��l�����āA�N��������s��Ђ�I�ԂƂ悢�ł��傤�B
�X�e�b�v�B�e�폑�ނ̒ʒm��t������
��Ƃ����o�������������ƂɌv�Z���s���Ă��炢�A12�����̋��^�̋��z�������^�x�����̍쐬����������ΔN��������s��Ђ���ʒm�����܂��B
�v�Z�������ʁA�����ł��x�����߂��Ă���Ώ]�ƈ��̋��^����悹����A�x�����z������Ă��Ȃ�����^���璥������܂��B
���̌�ɁA������ŋ��ȂǍׂ��ȏ�L�ڂ��ꂽ�����[�̔��s�����Ă��炢�A���ނ��]�ƈ��{�l�ɓn���ΔN�������̋Ɩ��͏I���ł��B
�N��������s�𗘗p����ۂ̒��ӓ_
�N��������s�T�[�r�X�𗘗p���邱�Ƃ́A��ƂɂƂ��đ����̃����b�g�������炵�܂����A�˗��ɍۂ��Ē��ӂ��ׂ��_�����������݂��܂��B
�N�������͔N�Ɉ�x�̋Ɩ��ł���A���m���ƃX���[�Y�ȏ��������߂��邽�߁A�K�Ȉϑ����I�Ԃ��Ƃ��d�v�ł��B�ȉ��ɁA�N��������s���˗�����ۂɊm�F���Ă��������|�C���g��������܂��B
���i�̑Ó������m�F����
�N��������s�̔�p�͋Ǝ҂ɂ���Ă��܂��܂ł��B��{�����ɉ����ăI�v�V������p����������ꍇ������A�z��O�̏o��������邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B��s���˗�����O�ɂ́A�����T�[�r�X���e�Ɖ��i���������Ă��邩�A���ЂƔ�r���đÓ��ȋ��z�ł��邩���m�F���܂��傤�B�R�X�g��}����������Ƃ����āA�K�v�ȃT�[�r�X���s�����Ă���Ǝ҂�I�ԂƁA���ʓI�ɕʓr��p����������\��������܂��B
�܂��A�����̌n���`�F�b�N���Ă������Ƃ���ł��B�Ⴆ�A��{�I�ȔN�������ɕK�v�ȍ��ڂ݂̂��˗��������ꍇ�ƁA�}�{�T����ی����T���Ȃǂ̒lj��Ɩ����K�v�ȏꍇ�Ƃŗ������قȂ�P�[�X������܂��B�����̋Ǝ҂��猩�ς�������A��p�Ό��ʂ��l���������œK�ȋƎ҂�I�т܂��傤�B
���Z�L�����e�B��S�ۂł��邩���ӂ���
�N�������ɂ͏]�ƈ��̌l������܂܂�Ă��܂��B�˗������s�Ǝ҂����Z�L�����e�B����\���ɍu���Ă��邩���m�F���邱�Ƃ́A��ƂƂ��Ă̐M���ێ��ɂ��d�v�ł��B�Z�L�����e�B���Ǝ�ȋƎ҂Ɉ˗�����ƁA���R�k�̃��X�N�����܂�A�]�ƈ��̐M���Ȃ������łȂ��A�@�I�Ȗ��ɔ��W����\��������܂��B
�Ǝ҂��ǂ̂悤�ȏ��Ǘ��V�X�e�����̗p���Ă��邩�A�f�[�^�Í�����A�N�Z�X�������s���Ă��邩�����O�Ɋm�F���܂��傤�B�܂��A������̎��̂ɔ������Ή����A�v���C�o�V�[�}�[�N��ISMS�F�ȂǁA�O���F���擾���Ă��邩���Z�L�����e�B�̖ڈ��ƂȂ�܂��B���Ǘ����O�ꂳ��Ă���Ǝ҂�I�Ԃ��ƂŁA���S�����S�ȔN��������s���˗����邱�Ƃ��ł��܂��B
���ނ̒�o��������t�Z���Ĉϑ����I�肷��
�N�������̏��ޒ�o�ɂ͊��������邽�߁A�˗����I�ԍۂɂ͏\���ȗ]�T�������đI�肵�A�Ǝ҂ɕK�v���ނ��o�ł���̐��𐮂��܂��傤�B�Z�����N���̎����͋Ǝ҂��˗����W�����₷���A���ɑΉ����x��Ă��܂��ƒ�����Ƃɉe�����o��\��������܂��B���������āA�N���̃X�P�W���[�����t�Z���Ĉ˗���i�߂邱�Ƃ���ł��B
�����Ɉ˗����邱�ƂŁA�Ǝ҂̏����������A���ނ̕s����m�F��Ƃ��X���[�Y�ɐi�߂邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�Ǝ҂Ƃ̑ł����킹��Ɩ��t���[�̊m�F�Ȃǂ����߂ɍs���A�o�����~���ɋƖ���i�߂���悤�������Ă����ƈ��S�ł��B�K�ȃ^�C�~���O�ň˗����邱�Ƃ́A�N����������Ȃ��������邽�߂̏d�v�ȃ|�C���g�ł��B
�ŗ��m�ɂ����ł��Ȃ��Ɩ������邱�Ƃ�m���Ă���
�N�������Ɋ֘A����Ŗ��Ɩ��̈ꕔ�́A�ŗ��m���i�����҂ɂ����Ή��ł��Ȃ����̂�����܂��B�Ŗ����k��A���G�Ȑŋ��v�Z�����������ꍇ�ɂ́A�ŗ��m�łȂ���ΑΉ��ł��Ȃ��ꍇ�����邽�߁A�K�v�ɉ����Đŗ��m���i�����Ǝ҂�I�ԂƂ悢�ł��傤�B���ɔN�������Ɋ֘A����Ŗ����k��ŋ��v�Z�́A�Ŗ��̒m�����[���ŗ��m�̕������m�ɑΉ��ł��܂��B
��ʓI�ȑ�s�Ǝ҂͔N�������̊�{�I�Ȏ葱���Ɋւ��Ă͑Ή��\�ł����A�Ŗ����������G�ȏꍇ�ɂ͐ŗ��m���ݐЂ��Ă���ƎҁA�������͕ʓr�ŗ��m���˗����邱�Ƃ���������Ɨǂ��ł��傤�B�Ŗ��Ɩ��̐��x��M�������m�ۂ��邽�߂ɂ��A�ŗ��m�̃T�|�[�g�����邩�ǂ������m�F���Ă����ƁA������̑Ή����\�ɂȂ�܂��B
�N��������s��3�̈˗���
�N��������s���˗��ł����Ђ́A�o���A�E�g�\�[�V���O��Ђ�ŗ��m�������A�ИJ�m��������3������܂��B
���ꂼ��������قȂ邽�߁A���Ђ������d�v�����Ă���̂��őI�т܂��傤�B
�˗���@�o���A�E�g�\�[�V���O���
�o���A�E�g�\�[�V���O��ЂɔN��������s���˗����郁���b�g�́A�R�X�g�̈����ł��B
�ŗ��m��������ИJ�m�������͌ږ◿�Ƃ����`�Ŕ�p���x�����܂����A�o���A�E�g�\�[�V���O��Ђ͏]�ƈ�1�l������Ŕ�p���x�������Ƃ��������߁A�R�X�g�������Ȃ�܂��B
���ɁA�l�������Ȃ��X�^�[�g�A�b�v�̉�Ђ�A���o�C�g��p�[�g�̕���������ƂȂǂ́A��p�Ό��ʂ������Ȃ�ł��傤�B
�܂��A�o���̃v���ɔC�����邱�ƂŔN�������ɂ���Ƃ̕��S�y���ƃ~�X�̖h�~���ł��邱�Ƃ��A�傫�ȃ����b�g�Ƃ����܂��B
����f�����b�g�́A�o���A�E�g�\�[�V���O��Ђɐŗ��m���ݐЂ��Ă��Ȃ��ꍇ�͐ߐł⏕�����̃A�h�o�C�X�����Ȃ����Ƃł��B
�Ȃ��ɂ͐ŗ��m���ݐЂ��Ă���o���A�E�g�\�[�V���O��Ђ�����܂����A�ݐЂ��Ă��Ȃ��ꍇ�����邽�߁A���O�ɂ�������Ɗm�F���Ă����܂��傤�B
�N�������̋Ɩ����S���y�����邽�߂ɁA�����R�X�g��������Ɩ{�ƂɃR�X�g�������Â炭�Ȃ��Ă��܂��܂��B
���̂��߁A�����R�X�g�ŔN��������s���˗��ł���o���A�E�g�\�[�V���O��Ђւ̈˗����������߂ł��B
�֘A�L�������o���Ƃ́H�Ɩ����e�⏑�ނ̎��
���ቿ�i�ő����E�풓�\�Ȍo���A�E�g�\�[�V���O��
�˗���A�ŗ��m������
�ŗ��m�������́A�ŋ��Ɋւ���@���ɋ����Ƃ��������b�g������܂��B
���̂��߁A�ŗ��m�������ɔN��������s���˗����邱�ƂŁA�ߐł̃A�h�o�C�X�����炤���Ƃ��ł��܂��B
�܂��A�������ŋ��̐\�����s���Ă��邩������Ŗ��������������ꍇ���ŗ��m�������ɑΉ����Ă��炤���Ƃ��\�ł��B
�������A�ߐł̃A�h�o�C�X������悤�Ȑ��I�Ȓm���̂���ŗ��m�Ɉ˗�����̂ł���A�ږ◿�͍����Ȃ�Ƃ����f�����b�g������܂��B
�܂��ŗ��m�́A�l�̈Č��ɋ����ŗ��m�Ɩ@�l�̈Č��ɋ����ŗ��m�ɕ�����܂��B
�l�̈Č��ɋ����ŗ��m�ɔN��������s���˗����Ă����܂胁���b�g�������ł��Ȃ��\�������邽�߁A�N��������s���˗�����ۂɂ́A�@�l�̈Č��ɋ����ŗ��m�Ɉ˗����܂��傤�B
�˗���B�ИJ�m������
2016�N�ɐŗ��m�ƎИJ�m�̋Ɩ��͈͂����m�ɂȂ�A�N�������̋Ɩ��͐ŗ��m�̎d���ƔF�肳��A�ИJ�m���N��������s���s�����Ƃ͐ŗ��m�@�ᔽ�ƂȂ�܂����B
�������A�ŗ��m�������Ƌ��͊W�ɂ���ИJ�m�������́A�N�������Ɩ����s�����Ƃ��\�ł��B
�ИJ�m�������́A��ɋ��^�v�Z���˗����Ă���ꍇ�ɒlj��ŔN���������˗��ł��邱�Ƃ�����܂��B
���̂��߁A�ИJ�m�̋��݂ł����鏕������⏕���ɂ��ẴA�h�o�C�X�����炦�邱�Ƃ̓����b�g�ɂȂ�܂��B
�N��������s��Ђ̔�p�̖ڈ�
�o���̐��I�Ȓm�����������o���A�E�g�\�[�V���O��ЂɈ˗������邱�ƂŁA�Ɩ��̕��S������r�W�l�X�����������邱�Ƃ��\�ł��B
�N��������s�̗����̌n�́A��{�����Ə]�ƈ�1�l������̗����𑫂�����Ђ������ł��B
��{�����̑���̖ڈ���1�`3���~���x�ŁA�]�ƈ�1�l������̗�����1��`3��~���x�ƂȂ�܂��B
���Ƃ��A�]�ƈ�20�l���x�̉�Ђ��N��������s���˗�����ꍇ�A9���~���x�ň˗��ł���̂ł��B
�]�ƈ����������Ȃ�Ȃ�قǔN��������s�ɕK�v�Ȕ�p�������܂����A���̕��N�������̍�Ƃɂ����鎞�Ԃ��팸�ł��܂��B
�N��������s�̔�p��}�������ꍇ�́A��r�I�v�Z���₷���A���o�C�g��p�[�g�̕��̔N�������͎��Ђōs�����Ј��̔N���������s���邱�Ƃ��������߂ł��B
���ቿ�i�ő����E�풓�\�Ȍo���A�E�g�\�[�V���O��
�N��������s�Ɋ֘A����T�[�r�X�̎�ނƖڈ��̔�p
�N��������s�Ɋ֘A����T�[�r�X�ɂ́A�L����s�ƌ��Z��s������܂��B
�L����s�Ƃ́A���Ђ̌o���Ɩ��̈ꕔ�ł���L�����O���@�ւɃA�E�g�\�[�V���O���邱�Ƃł��B
�L����s�̔�p�̑���́A�u�d�ɂ���p���ς��v�ꍇ�ƁA�u1���Ԃ�����̗������v�̏ꍇ�ɂ���ĕ�����܂��B
�u�d�ɂ���p���ς��v�ꍇ�́A1�d����50�`100�~��1�̖ڈ��Ƃ��āA���z1�`3���~�قǂ�����܂��B
�u1���Ԃ�����̗������v�̏ꍇ�́A2���Ԃ�����1���~���x����̗��p���\�ł��B
�܂����Z��s�Ƃ́A���Z�ɕK�v�Ȍ��Z����\�����̍쐬�A�Ŗ����ւ̐\�����s���Ă����T�[�r�X�ł��B
���Z��s�̔�p�̖ڈ��́A�ǂ��܂ł̍�Ɠ��e���˗����邩�ɂ���đ傫���ϓ����܂��B
�N��������s����������Ă�����ł��Ɩ��ɂ����镉�S���y�����������́A�L����s�⌈�Z��s����������Ƃ悢�ł��傤�B
�֘A�L�������o���A�E�g�\�[�V���O�i��s�j�̗����E��p����
�L����s�Ƃ́H�Ɩ����e����b�g�E��p����
�L���Ƃ́A��Ƃ̎����ɂ��邱�Ƃ��w���܂��B
2014�N��蔒�F�\���E�F�\�����킸����Â����@�I�ɋ`�������ꂽ���ƂŔY�܂�Ă���o���̕��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̒���Â��̍�ƕ��S��}���邱�Ƃ��ł���T�[�r�X���A�L����s��ЂL�����ϑ��ł���L����s�ł��B
�o���S���҂��s�݂̏ꍇ��X�^�[�g�A�b�v��Ƃ̏ꍇ�ȂǁA�V���ɏ]�ƈ����ق������\�肪������́A�Ɩ����~���ɐi�߂邽�߂ɂ��L����s���������Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B
���L��URL�ł́A�L����s�̃T�[�r�X���e�ƃ����b�g���p�̑���ɂ��ďڂ���������Ă��܂��̂ŁA�C�ɂȂ���͂��Ђ������������B
�L����s�Ƃ́H�Ɩ����e����b�g�E��p����
�o���A�E�g�\�[�V���O�Ȃ瑦���E�풓�\��RSTANDARD��
�u�o���S���҂��ˑR�ސE���Ă��܂����v�u�l��s���ŃR�A�Ɩ��܂Ŏ肪���Ȃ��v�Ƃ�����̕��́ARSTANDARD�ɂ����k���������B�����E�ቿ�i�Ő�C�R���T���^���g���풓�E�K�₵�A�����E�������猈�Z�A���|�[�g�E�\���܂ł�����ɍ��킹�Ē����Ɉ����p���܂��B
�lj���p�Ȃ��ŋƖ��}�j���A�������A�������܂Œ��J�Ɏx�����܂��B�l���m�ۂ�����ꍇ�͎��Љ^�c�̌o���h���ő���͂����Љ�܂��B�Ɩ����P��IPO�E���������A��v�V�X�e���̌������ɂ��Ή��ł��܂��̂ŁA�܂��͂��C�y�ɂ����k���������B
���ቿ�i�ő����E�풓�\�Ȍo���A�E�g�\�[�V���O��
�N��������s�𗘗p���邱�ƂŔN�������ɂ������Ƃ̕��S�����炷���Ƃ��ł���
�������ł����ł��傤���H
�N��������s�Ƃ́A�N�������Ɋ֘A�����Ƃ��O���Ɉϑ�����T�[�r�X�ł��B
�N�������ɕK�v�Ȏ����̊m�F��T���z�ƌ��������̌v�Z�A�ڋq�ւ̌��ʂ̒ʒm�܂ł��s���Ă��炦�܂��B
�N��������s���˗��ł����Ђɂ́A�o���A�E�g�\�[�V���O��Ђ�ŗ��m�������Ȃǂ�����܂����A�˗������Ђ̎�ނɂ���ē������p���قȂ�܂��B
�N�������Ɩ��̏��m�F���āA�Ɩ��ߑ��ɂȂ��Ă���悤�ł���ΊO���Ɉϑ����邱�Ƃ��������߂ł� �B
�֘A�L�������o���Ɩ���IT�����闝�R�Ƃ́H��������3�̒��ӓ_��c�����悤
�o���A�E�g�\�[�V���O�E��s�Ȃ瑦���E�ቿ�i��RSTANDARD�ւ��C�����������B
�o���A�E�g�\�[�V���O�ɂ��ďڂ����m�肽�����͈ȉ��̂������ߋL�������Ђ������������B
�������ߋL���F�o���A�E�g�\�[�V���O�Ƃ́H�����b�g�E�f�����b�g�ƋƎ҂̐������I�ѕ�
- �L����s�Ƃ́H�Ɩ����e����b�g�E��p����
- �o���A�E�g�\�[�V���O�i��s�j�̗����E��p����
- ���|���̉����s�Ƃ́H�������b�g�E���ӓ_
�o���A�E�g�\�[�V���O�Ɋւ���
�T�[�r�X�ڍׂ͂�����